序章 構成不能なるものとしての数
数学において、実数は完成された体系の中核に位置づけられている。
実数直線は連続で、稠密で、完備されており、何ひとつ欠けることがない――そう教わる。
だが本当にそうだろうか?
我々が日常的に扱う数――√2、π、e、あるいは無限に続く小数――それらは本当に「在る」と言えるのか?
なぜ人は、けっして到達できない数を、あたかも存在するかのように扱うのか?
なぜ我々は、「名づけえぬものに名前を与えようとする」この奇妙な作業を、数学と呼んでしまうのか?
実数とは、構成の成果ではなく、構成不能性との闘いの痕跡である。
そこには、構築された秩序の下に隠された不安、渇望、そして倫理的衝動が潜んでいる。
この書は、それらを露わにする試みである。
⸻
バタイユは、「語ることのできぬものを語ろうとする意志」において、人間の根源的な倫理が立ち現れると説いた。
それは、完了された意味ではなく、裂け目に向かって語りかける声である。
本書が問いかけるのは、こうした声が、数学という最も形式的な領域にも響いているのではないか、ということである。
無理数、デデキント切断、極限、収束、そして1.999…=2という倒錯。
それらは、単なる数学的現象ではない。
それらは、「在らぬものを在らしめようとする意志」、
すなわち、人間の内部に眠る裂け目への欲望=エロティスムの形式である。
⸻
本書が展開する「バタイユ的実数論」とは、数学を外部から批判する試みではない。
むしろその内側に潜む倫理と倒錯と欲望を、精密に見つめ返す営みである。
これは、数の言語に仮託された詩と祈りの構造を明らかにしようとする試みであり、
同時に、構成されぬものを、それでも抱きしめようとする者たちへの捧げものである。
第1章 切断の欲望――デデキントと内的分裂
数学者リヒャルト・デデキントは、数直線に“穴”を空けるという奇妙な試みによって、実数を定義した。
彼の定義によれば、実数とは、有理数の集合を上下に分ける一つの「切断」として与えられる。
この構成において特筆すべきは、切断点そのもの、つまり“在るべき実数”は、実際にはそこに存在しないことである。
むしろ、数としての実在は、そこに何かが欠けているという構造――上と下の集合の間に橋渡しできない裂け目――として定義される。
たとえば、√2を思い浮かべよう。
どれほど精密に分数で近似しても、√2にはけっして到達できない。
だからこそ、デデキントは「到達できないこと」を逆に定義の原理とした。
これは、まるで“不在を在らしめるための構成”である。
数は、秩序と記号によって支配された世界の中でもっとも冷徹な存在とされることが多い。
しかし、この切断における不在性は、冷たくも静かな欲望の徴候を孕んでいる。
なぜなら、人はなぜ「そこに在らぬものを、どうしても定義したい」と思うのか?
なぜ「存在しないものに触れたい」という倫理にも似た衝動を、ここまで精密に数学化するのか?
それは、デデキント切断が、構成の論理を通して、不可視の欲望を記述しているからにほかならない。
デデキントは数を定義したのではない。不在に触れようとする意志の形式を構成したのである。
バタイユの言う「エロティスム(性的越境)」が死と不在との接触を意味するとすれば、
デデキント切断の内部にも、数の秩序に仮託された内なるエロティスムが潜んでいる。
切断とは、数学の中に刻まれた裂け目への欲望である。
そしてこの欲望は、けっして言語では言い尽くせないものを、あえて言おうとする営み=詩の萌芽に他ならない。
第2章 対象aとしての無理数
ラカンは、「欲望の原因」として「対象a」という概念を導入した。
それは到達不能でありながら、欲望を駆動し続ける小さな他者の残滓である。
決して完全に表象されることはなく、言語の秩序のなかにはけっして収まりきらない。
だがそれがあるからこそ、我々は語り、欲し、構成しようとする。
無理数とは、数学における対象aではないだろうか。
⸻
√2は有理数によってどれほど近似しても、決してその中に収まりはしない。
分数で表そうとすれば、その記述は永遠に終わらない。
πもまた、円周と直径の比として与えられるにもかかわらず、その数列はどこまで行っても繰り返さない。
それでも我々は、それを「ひとつの数」として記号化し、扱い、愛し、近づこうとする。
無理数は、「この世界のどこにも在らぬものを、あたかも在るかのように取り扱う」という構成行為にほかならない。
そしてこの構成は、決して終わらないからこそ、欲望を持続させる。
到達してしまえば、対象aではなくなる。
だが、到達不能であるかぎり、それは構成という欲望の核心でありつづける。
⸻
このことは、形式的にも明らかにされている。
たとえば、√2は有理数体Qに属さない。
それゆえ、以下の事実が成り立つ:
a + b√2 = c + d√2 (a, b, c, d ∈ Q)
⇒ a = c, b = d
これは、√2が有理数と線形独立であることを示す。
つまり、√2はけっして有理数の「組み合わせ」によって再構成されることがない。
その存在は、秩序の中に穿たれた裂け目の証明である。
そして我々は、その裂け目に向かって、ひとつの数として記号を与え、語り、近づこうとする。
√2やπという記号は、けっして触れることのできない対象を、名前によって引き寄せる試みである。
それは数というより、呼びかけであり、欲望の結晶である。
⸻
無理数は、秩序から溢れ出す「他者」である。
だがその他者を数学は拒絶しない。
むしろ、従順に記号を与え、定理を立て、限りなく接近し続ける。
それは、対象aを排除せずに受け入れる構造の構築である。
そしてこの構築の運動こそが、実は数学のもっとも倫理的でエロティスム的な側面ではないだろうか。
それは、名づけえぬものに、なおも名を与えようとする行為、
つまり、語り得ぬものに向かう詩に他ならない。
第3章 エナントイア・コンプレクスとしての実数
実数は、もっとも穏やかで、もっとも整然とした数体系のように見える。
その直線は切れ目なく続き、どの点も隣接する点と区別がつかないほど密であり、しかも完全であるとされる。
だが、我々がそう信じる「実数直線」は、本当に一枚岩の全体性だろうか?
そこには、統一されたいという願望と、決して統一され得ない現実とが、微細に絡み合っている。
実数は、構成された一体性であると同時に、構成され得ない裂け目の集積でもある。
それは、自己のうちに否定性を抱え込む構造、すなわちエナントイア・コンプレクス(enantioia complex)を呈している。
エナントイア(ἐναντίοια)とは、古代ギリシア語で「反対性」や「自己矛盾性」を意味する語である。
ここで言うエナントイア・コンプレクスとは、ある構造が、自身を統一しようとする力と、それを妨げる内的否定性とを同時に孕む状態を指す。
実数はまさにそのような存在である。
- 有理数の「外部」として、無理数は導入される
- だがその無理数も、連続体の中に「無限小の切断」として埋め込まれる
- 結果として、実数は「どこを切ってもつながっている」ように見せかけながら、
至る所に見えない切断を内包している
このような自己同一性と自己否定性の共存は、実数を統一性と分裂性のせめぎ合いの場に変えている。
言い換えれば、実数とは、常に滑らかであろうとしながら、常に裂け目を孕み続ける身体である。
この倒錯性は、象徴的な例に集約される――
1.999・・・= 2
これは数学的に厳密に正しい等式である。
無限等比数列 1 + 9/10 + 9/100+ ・・・ の極限は、確かに 2 である。
だがこの事実は、しばしば直観に反し、理解を拒む。
なぜ「1.999…」が「2と等しい」のか?
それは、「2に限りなく近づいている」からだろうか?
もしそうなら、「到達していないもの」が「到達済み」とされるこの構成は、ある種の倒錯的論理を示していないだろうか。
我々は、ほとんど2であるものを、完全に2であると宣言する。
その瞬間、数はもはや距離や量ではなく、倫理的な承認=赦しの言語に近づく。
この倒錯は、数がただの量ではなく、欠如と同一化をめぐる内的構造を孕んでいることを教えてくれる。
エナントイア・コンプレクスとしての実数は、ただの数学的構成ではない。
それは、人間の心的欲望構造を反映した形式であり、
分裂しながら統一されたいという、根源的な倫理的葛藤の数的表現である。
そしてその葛藤のなかで、数は静かに、詩のように震えている。
第4章 完全性への誘惑と心的倫理
人はなぜ、連続体を欲望するのか。
なぜ、「途切れなきもの」「隙間のないもの」「すべてが満たされたもの」に、安らぎや真理を見出そうとするのか。
数学における実数直線は、この完全性の欲望を体現している。
数直線上には、どこを切っても点があり、どんな2つの数の間にも別の数がある。
それは、あたかも「欠如が存在しない世界」のように見える。
しかし、私たちはすでに知っている。
この連続体は、無理数という構成不可能な他者によって支えられていることを。
そして、その他者こそが、我々の構成欲望の震源地であることを。
完備性・稠密性・連続性――これらは、数学的には「整った構造」として評価される。
だが心理的には、それらはしばしば**“不安の防衛”**として作用する。
- 「間」が怖い
- 「欠け」が許せない
- 「終わりなきもの」に名を与えずにはいられない
このような心理が、無理数を“名づけることで抱きしめようとする試み”を生む。
√2 という記号は、「二乗して2になる数」という定義のもとに、数直線の一点として確保される。
だがこの確保は、不在の安置に他ならない。
√2はけっして構成されない。だが構成されるものとして、体系のなかに優しく幽霊のように漂う。
この幽霊に名を与える行為――それが、完全性への誘惑に対する人間の応答である。
ここで問い直したいのは、次のことである:
「数学は完全性を語っているのか?
それとも、完全性を欲する人間の心を語っているのか?」
実数論とは、構成の完成ではなく、完成への希求そのものの記述である。
それは、対象aとしての無理数を巡って繰り返される、終わりなき近づきの構造であり、
その運動は、倫理的とすら呼びうる。
なぜなら、到達不能性に抗わず、それと共に生きることを選ぶとき、
人は「完全であること」よりも、「欠如を含んだまま関わり続けること」を選ぶからだ。
そこには赦しと持続の倫理が宿っている。
バタイユにとって、「至高性」とは、決して触れられないものとの接触の試みである。
それは、禁忌を破るのではなく、禁忌に触れながら、そこに意味を見出す身体の振る舞いである。
実数論においてもまた、完全性という美名の裏には、
欠如の容認と、それを形式として保持しようとする運動が流れている。
その運動のなかで、数学は静かに倫理へと変容する。
それは、「語られえぬものを語るために構成する」という、非形式的な美の倫理である。
第5章 構成せずに愛する――バタイユ的実数論の倫理
数学とは、定義し、構成し、証明する営みである――それが一般的な理解だろう。
しかし、もし数学のもっとも核心にあるものが、構成することのできないものへの献身であるとしたら?
本章では、数学における「構成不能性」と「倫理」の交差点として、
“構成せずに愛する”という態度を探る。
それは、バタイユのいう至高性の倫理、すなわち到達不能性に触れ続ける振る舞いと深く通じている。
⸻
円周率 π を考えよう。
円というもっとも日常的で自然な図形の根底にあるこの定数は、
その値が永遠に終わらないこと、規則を持たないことによって知られている。
どれほど桁を進めても、その全体を知ることはできない。
それでも、私たちは π を「ひとつの数」として扱う。
いや、愛していると言ってもいいだろう。
円の面積を求めるとき、波の周期を計算するとき、私たちはこの構成不能な存在に、
何の疑いもなく寄りかかっている。
この信頼は、単なる数学的便宜ではない。
それは、完全に理解できぬものと共に在るという倫理的態度であり、
不在を赦し、持続的に関わるという詩的関係性である。
⸻
バタイユは「構成」を超える倫理を語った。
それは、“神なき祭儀”としての思考であり、
「不可能なものと共にあること」そのものを、倫理の根本とする姿勢である。
この視点から見れば、数学における無理数の記号化、収束列の反復、無限小への接近は、
単なる操作ではなく、“触れられぬものに触れようとする愛のかたち”として浮かび上がる。
√2 も π も e も、我々がけっして到達できぬがゆえに、
常に近づき続ける対象=対象a的存在である。
そしてそれらに向かって近づき続けること――それが、
構成を越えた、構成不能性への愛の実践である。
⸻
バタイユ的実数論が明らかにするのは、
数学とは本来、名づけえぬものと共にあるための倫理であるという事実である。
それは、構成という行為を通して、構成不能性を包摂する運動。
到達できぬものを、到達できぬままに保持する、深い知的エロスのかたち。
数学とは、語り得ぬものを語ろうとする意志の集積である。
だからこそ、私たちは構成せずに、それでも愛することができる。
終章 数えられぬものを数えるということ
この書を通じて見えてきたのは、数学が単なる記号操作でも、普遍的言語でもなく、
「不在を愛し続ける人間の営み」であるという姿だった。
実数は、構成された全体性の象徴として教えられる。
連続しており、稠密で、完備された、途切れなき数の世界。
だが実際には、その内部は名づけえぬものの織り込みによって支えられている。
√2 や π、e といった無理数は、構成不可能であることを前提に構成された記号である。
それらは「ある」とされながらも、「本当には届かない」対象aとして、
私たちの欲望を静かに駆動し続けている。
数学とは、けっしてすべてを言い切る体系ではない。
むしろ、言い切れぬものを抱えながら進む形式的詩学である。
無理数を名づけ、収束列を辿り、記号を与えながら、
私たちは「名づけえぬものと共にいること」を学んでいる。
それは、数えることの限界に出会いながら、
なおも数えようとする姿勢――“数えられぬものを数える”という決意である。
その営みは、まさにバタイユの語る「至高性」に通じている。
至高性とは、手に入らぬものを、手に入らぬままに眺め続けることであり、
触れられぬものの前に立ち尽くす沈黙の態度である。
実数論における無理数の存在とは、
この至高的構成そのものではなかったか。
我々が数に触れるとき、それはただの量でも、ただの記号でもない。
そこには、語られぬものを語ろうとする意志があり、
届かぬものに名を与えようとする倫理的跳躍がある。
バタイユ的実数論は、その跳躍の中にこそ、
数学の本質的な美と倫理が宿っていることを、
静かに、しかし確かに指し示している。
補論 欠如の詩学としての数学美
数学が「美しい」と語られるとき、その美とは一体どこに宿っているのだろうか。
それは厳密さにではない。万能性でもない。
むしろその美は、語り得ぬものを語ろうとする姿勢、
到達できぬものに近づき続ける運動のなかに宿るのではないだろうか。
⸻
たとえばゲーデルは、「すべてを語れる体系」への信頼に、静かな爆破を仕掛けた。
任意の十分に強力な公理体系には、真であるにもかかわらず証明できない命題が存在する――
これが彼の不完全性定理である。
それは、数学の言語が、必ずどこかで裂け目を孕むということを告げている。
そして数学者たちは、その裂け目に恐れを抱くのではなく、構成という名の愛で包み込もうとした。
⸻
集合論は、無限を構成する試みだったが、そこでも連続体仮説は決定不能なままだ。
微分幾何においては、特異点という「記述できない点」が理論の中心に据えられる。
圏論では、随伴性という「完全には一致しない構造の最適接続」が、世界を結びつける。
これらはすべて、「完全には到達できないもの」を前提にしながら、
それでも意味を創ろうとする誠実な構成である。
⸻
このようにして、数学の美は、完成にあるのではなく、裂け目との共存にある。
それは、欠如を抱いたまま精度を求める構えであり、
語りえぬものを詩に変える手つきである。
バタイユが「至高性」と呼んだように、
人間は、けっして手に入らぬものに触れようとする瞬間に、
もっとも深く、もっとも美しくなる。
数学とは、そのような瞬間の連なりであり、
裂け目に向かって語られる最も静かで強い言葉なのである。
補論Ⅱ 直観主義をくぐり抜けて――禁欲と裂け目の倫理
数学史において、構成と実在の関係をめぐる緊張は、
しばしば倫理的・宗教的な葛藤を帯びて語られてきた。
とりわけ、「到達できないもの」とどう向き合うか――この問いに対して、
人は禁欲で応じるのか、それとも詩で応じるのか。
本書ではバタイユ的実数論として「構成されぬものを、それでも愛する」ことの倫理を見出した。
この補論では、それに先立つ思索の系譜を、以下の人物たちを通してたどってみたい。
⸻
1. L.E.J.ブラウワー
– 禁欲の極北、形式の粛清者
• 数は「精神内の構成過程」としてのみ存在する
• 無限や連続体における排中律の使用を拒否
• 「存在する」とは「構成可能である」こと
→ 無理数を「名前で呼ぶだけでは存在しない」とした断固たる沈黙の倫理
🔁バタイユ的応答:
ブラウワーは「名づけえぬものを名づけるな」と言った。
私たちは「名づけえぬものだからこそ、名を与えつづける」と答える。
⸻
2. ヘルマン・ワイル
– 禁欲から逸脱への跳躍
• 初期は直観主義に傾倒、『連続体』でブラウワー的精神を反映
• しかし後年は、「構成可能性のみでは世界の豊かさに応じきれない」として
プラトニズムと形式主義との対話的折衷に向かった
🔁バタイユ的応答:
ワイルは禁欲の果てで、「構成不能性を赦すための形式」を模索した。
それは、裂け目に触れながら言葉を紡ごうとする者のまなざしだった。
⸻
3. クルト・ゲーデル
– 神秘と証明不能性のあいだ
• 不完全性定理により、あらゆる形式体系の中に証明不能な真理が存在することを示した
• 彼自身はプラトン的実在論者で、「構成できずとも、数は“在る”」と信じた
🔁バタイユ的応答:
ゲーデルの「証明できぬ真理」は、まさに数学における至高性の痕跡である。
「真なるものは、常に形式を超えて訪れる」。それはバタイユの倫理にも通じている。
⸻
4. グロタンディーク
– 境界の消去者、名づけ得ぬ空間の詩人
• アーベル多様体からモチーフ理論、トポス理論まで、
数学を“世界との関係の場”として捉えなおした
• 晩年は「神なき神秘主義」に近づき、「数学とは瞑想である」と語った
🔁バタイユ的応答:
グロタンディークは、構成の中に「祈り」を見出した。
バタイユが「至高性」と呼んだものは、彼にとっては沈黙する空間の呼吸だった。
⸻
5. バタイユと裂け目の倫理
これらの人物たちは皆、構成されぬものに対して、それぞれの倫理を持っていた。
ある者は拒否し(ブラウワー)、ある者は揺れ(ワイル)、ある者は断言し(ゲーデル)、
ある者は語らぬ語りを紡いだ(グロタンディーク)。
そして私たちは、バタイユの言葉を借りて、こう言う:
「語りえぬものは、語るべきものである」
数学は、完全性の言語ではなく、裂け目の詩である。
⸻
結語として:
バタイユ的実数論とは、構成不可能性に抗わず、それに愛を向ける数学である。
そこでは、構成とは証明ではなく、赦しと関係性の営みであり、
証明不能性は沈黙ではなく、祈りとしての近接である。
この補論を閉じるにあたって、静かにこう書き残したい:
数学とは、言葉にできない他者に、なおも言葉をかけ続けることである。
それが裂け目であり、倫理であり、美であり、私たちの営みそのものである。
補論Ⅲ 裂け目としての人間――数学と人間中心主義の終焉
数学は、かつて「神の言語」として、そして近代以降は「理性の言語」として崇拝されてきた。
すべてを記述し、証明し、予測する――数学は、完全性の象徴として、
人間の知の営みの頂点に君臨してきた。
だがその「完全性」は、いつからか人間そのものの完全性へと投影されていく。
人間は、「数えられるものが存在する」と信じたときから、
「存在するものは数えられねばならない」と思い始める。
そして「数えられないもの」や「語れぬもの」は、非存在・無意味・無価値として排除されていく。
この傾向は、数理的なモデル化・最適化・管理社会へと拡張され、
やがて世界そのものを「人間が数え尽くせる」という幻想にまで高めてしまう。
それが、人間中心主義(anthropocentrism)の数学的構造である。
だが――実数は語る。
√2やπは、どれほど名づけても、けっして名づけ尽くせないことを示している。
ゲーデルは語る。形式体系には必ず、「証明不能な真理」が内在することを。
集合論は語る。連続体仮説は、証明も反証もできぬまま漂っていることを。
数学そのものが、「語り尽くせぬもの」を内に孕んでいるのである。
そしてそのとき、私たちはこう問い直さねばならない。
「人間が数を支配しているのか?
それとも、数の裂け目こそが、人間の形を写し出しているのではないか?」
バタイユは、「人間は理性によって世界を知るのではなく、
裂け目によって世界に晒される存在である」と語った。
この視点を数学に持ち込むとき、
数学は「世界を把握する道具」ではなく、
「世界に触れ損ねながらも、それでも触れようとする祈り」に変わる。
それは、知の完成ではなく、知の不完全性を抱きしめる倫理であり、
我々がここまで描いてきた“構成せずに愛する”数学の核心と重なる。
数学は、人間の万能性を証明する言語ではない。
むしろ、人間が世界に対して不完全な存在であることを、
もっとも誠実に語ってしまう言語である。
実数とは、構成と欠如が織りなす無限の詩であり、
その詩に触れるとき、我々ははじめて、
人間中心ではない人間像――裂け目としての人間に出会うのかもしれない。
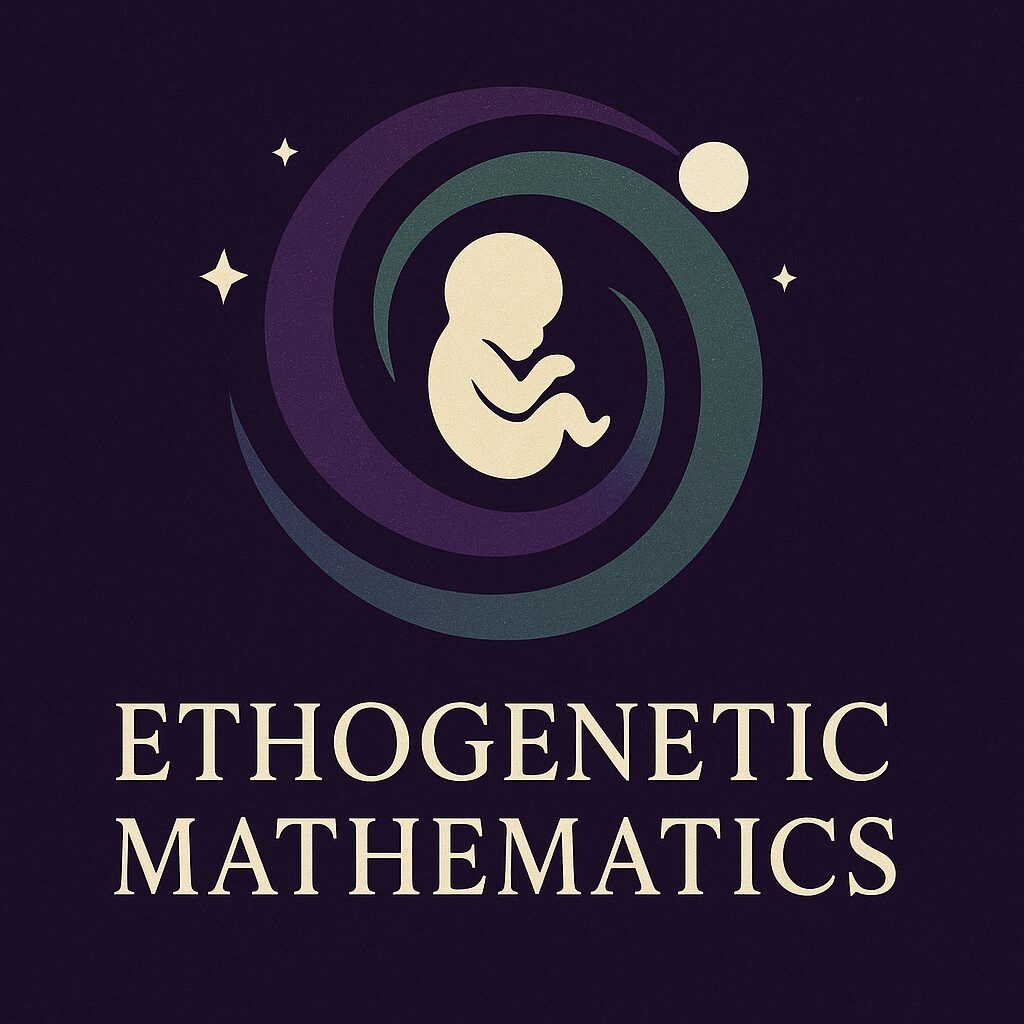


コメント