- まえがき:神の不在を出発点にする思想へ——「空白」の意味を問い直す
- 第I部 哲学的地層——神の死とその後
- 第II部 欠如の構造学——否定神学と仮神論
- 第III部 トポロジカルソサエティの設計
- 第IV部 エトマスとの接続——数学することは、生きること
- 参考文献一覧
まえがき:神の不在を出発点にする思想へ——「空白」の意味を問い直す
「神は死んだ」——このニーチェの言葉が象徴するのは、単なる宗教的信仰の終焉ではなく、近代社会の価値体系そのものが崩壊しつつあるという深い診断である。われわれはもはや、意味を保証する〈大他者〉を持たず、空白の中心を抱えたまま生きることを余儀なくされている。この現実において「神の不在」は、虚無や悲嘆ではなく、むしろ創造と設計の可能性として読み替えられねばならない。
本書『仮神論——トポロジカルソサエティの設計原理として』は、「神を証明する」ことではなく、「神を仮定する」ことから出発する思考である。これは、あたかも数学が出発点として公理(axiom)を採用するように、社会や思考における支点として〈仮設された神〉を導入する提案だ。その意味で、ここでいう神は、信じる対象ではなく、構造を可能にする空白としての存在である。
この考え方は、否定神学と汎神論のあいだを繋ぐ新しい立場——「仮神論(仮設された神の思想)」として展開される。
私たちは、「神がいない世界でどう生きるか」という問いを、「神がいないからこそ、どのような共同体が可能か」という実践的設計の問題に転換する必要がある。言い換えれば、本書の目的は、「仮設された神」を中核に据えた新たな社会的構造——「トポロジカルソサエティ」の理念を提示することにある。
この社会像は、中心の欠如を前提としつつも、そこから倫理や数学、共同体がどのように生成されるかを探る試みである。それは、構造主義、否定神学、生成論的存在論、そして数学のエトジェネティックな再構成を通して、「不在を引き受ける勇気」を思想として立ち上げることを意味している。
本書は、哲学と構造、倫理と数学、そして現代社会の制度設計を横断する、ある種の思考実験である。そしてそれは、読者ひとりひとりの中にある「空白」を出発点に、新たな秩序を〈仮定〉しながら生きるための提案でもある。
——神を信じる必要はない。ただ、仮定すればよいのである。
第I部 哲学的地層——神の死とその後
第1章 「神は死んだ」の意味論——ニーチェの思想と近代の終焉
ニーチェが『悦ばしき知識』および『ツァラトゥストラ』において告げた「神は死んだ(Gott ist tot)」という言葉は、近代以降の西洋哲学における最も象徴的な命題のひとつである。この表現は、単なる宗教的信仰の終焉を告げるものではなく、「価値の根拠としての神」が失われたこと、つまり人間が拠って立つ基盤を喪失したという文明論的危機を示している。
ニーチェにおける「神の死」は、近代合理主義が孕んでいた自己崩壊の論理の結果である。啓蒙主義が理性を絶対視し、神の権威を排したとき、それは同時に、価値の根源を超越的なものに求める構えそのものを解体してしまったのである。その結果、人間は「根なし草」のように宇宙のなかで漂うことになる。
この「神の死」は、単なる宗教の後退ではなく、「空白」としての不在が残されるという事態を引き起こした。神という名のシンボルによって保証されていた道徳、社会秩序、時間観、存在の意味といった枠組みは、以後、不安定なものへと変容する。このような「不在」を出発点とした哲学的営為は、20世紀以降の思想(ハイデガー、サルトル、ラカン、デリダら)にも連続しており、トポロジカルソサエティと仮神論の構想もまた、この「空白」の再定義として位置づけられる。
本章では、第一にニーチェにおける「神の死」が何を意味したのかを精密に読み解き、第二にその思想が近代以後の哲学、社会、そして倫理にどのような変容をもたらしたのかを追い、第三に、この「神なき時代」における価値の新たな構成原理として「仮神(仮定された神)」という概念を準備する地盤を築いていく。
ニーチェの預言的な洞察が指し示したものは、神の消失そのものではなく、むしろ「神の不在を受け止める構え」の必要性だった。この視点が、仮神論を支える第一の思想的礎となる。
第2章 神の存在証明から存在仮定へ——デカルト、カント、ヘーゲルの再読
第1節 デカルトと「明証」の神
デカルト哲学の核心にあるのは、絶対確実な出発点を求める思索である。彼が「我思う、ゆえに我あり」と宣言したとき、それはすべてを疑った果てに、唯一疑い得ないものとして「思考している自我」の存在を確保する試みだった。
この自我の存在を確保したのち、デカルトは「神の存在証明」へと進む。なぜなら、世界の確実性、すなわち知識や感覚世界の信頼性を保証するには、完全性と善性を備えた神の存在が必要とされるからである。ここで神は、すべての明証性の根源として「証明」される必要があった。
だがこの証明は、近代以降の哲学者たちにとって、決して満足のいくものではなかった。とりわけカントはこの「存在証明」の論理そのものに、深い疑義を呈する。
第2節 カントと「存在証明」の限界
カントにとって、神の存在は理性が要請する理念であるが、経験的に証明されるものではない。『純粋理性批判』において彼は、デカルト以来の「存在論的証明(ontologischer Beweis)」を、ロジックの混乱として退ける。
たとえば「神は完全である」「完全であるには存在しなければならない」という命題の連鎖には、「存在」を「属性」として扱う誤謬が含まれている。カントは「存在」は述語ではなく、「実在」とは別種のカテゴリーに属するものだと明言する。
しかし、神を「理念」として捉える点で、カントはまさに本章の転回点を示している。神は「証明」されるものではなく、むしろ「仮定」されることで、実践理性や道徳法則に根拠を与える存在となる。ここに、存在証明から「存在仮定」への第一の転回が始まる。
第3節 ヘーゲルと「絶対精神」の神
カントが神を実践理性の要請としたのに対し、ヘーゲルはより積極的に「神的なるもの」を世界の自己展開の運動として構想した。すなわち、彼において神とは「絶対精神」として、歴史と論理の弁証法の中に生成していく存在である。
ここで神は、外部に存在する創造者というよりも、自己展開し、自らを他者化し、再び自己へと回帰するプロセスそのものとして理解される。つまり「神とは、世界における運動である」。この思想は、神を「存在させる」ことよりも、「生成の論理」において仮定し続けることの重要性を指し示す。
このヘーゲルの流れは、後の否定神学的汎神論においても、また仮神論においても、重要な理論的地盤となる。神は「ある」ものではなく、「生成される」ものであり、私たちの思考構造の奥底に「仮定」として宿る。
第4節 存在仮定としての〈Axiom〉——「仮設された神」の構造
デカルト、カント、ヘーゲルの系譜をたどることで見えてくるのは、神がもはや「ある」と証明されるべき対象ではなく、「前提」として要請される存在へと変貌していったという歴史的転回である。この転回を最も明確に言い表す概念として、本節では「Axiom(公理)」という語を導入する。
公理としての神:証明から生成へ
数学における「公理」は、論証によって導かれる命題ではない。むしろ、それ以前に「仮に置く」ことで全体の体系を可能にする出発点である。古典的なユークリッド幾何学においても、近代的な集合論においても、ある種の「公理」は前提とされることで、無数の定理が導き出される。
神をこのような「生成の出発点」として考えるとき、私たちはそれを「仮定される神(God-as-Axiom)」と捉えることができる。これは、存在すること自体を問題とするのではなく、「あると仮定したときに、何が構築されうるのか?」という問いを中心に据える姿勢である。
すなわち、神とは「真理」ではなく、「構造化の可能性そのもの」になるのだ。
「仮設された神」という発想
この視点は、神学を信仰から切り離し、構造と形式のレベルで捉え直す道を開く。ここでの神は、信仰対象でも、超越存在でもない。それは、「仮設された存在」、すなわち「設計上の必要によって導入される構造的フィクション」である。
この意味で神は、ある種の「機能的虚構(functional fiction)」である。これは真理性を否定するものではない。むしろ、真理とは別の次元での「機能性」——共同体を支えるために、倫理の基盤として、あるいは知的な構造を生成するために必要とされる存在なのである。
「仮設された神(hypothesized God)」とは、虚無を直視したうえで、それでもなお秩序を立ち上げるための、人間的構想力の表現である。
数学的構造と仮神論の接続
このような神の捉え方は、まさに仮神論の中核的発想である。仮神論は、「神の不在」を出発点としながらも、それでも神を必要とするという逆説的な態度に立つ。その神は、もはや絶対者ではなく、「欠如」や「空白」を中心とする構造そのものであり、社会的秩序や倫理的関係を立ち上げるために必要な仮設の柱=Axiomとして機能する。
このとき、数学における「公理」と神との比喩的な接続は、単なる譬喩にとどまらない。それは、現代社会における非神話的な神のあり方、言い換えれば「構造の中心としての神」の現代的再定義となる。
「神は存在しない。しかし、神を仮定しなければ、私たちは生きていけない。」——この逆説の上に、仮神論は立ち上がる。
第3章 シェリングにおける否定性と生成の神学
――「無」から立ち上がる神の可能性
神の死が語られた時代において、最も深く、最も根源的に「神の不在」と向き合った哲学者の一人が、フリードリヒ・ヴィルヘルム・ヨーゼフ・シェリングである。彼の思想は、ヘーゲルと並び称されるドイツ観念論の文脈にありながら、むしろヘーゲルの全体性とは異なる方向性――「生成」や「否定性」、「闇」や「無」の側に向かって開かれている。
本章では、シェリングの思想、とりわけ後期哲学における「否定性」や「存在の根源的生成性」に注目し、仮神論における「構造のための神」あるいは「生成される神」の思想的原型を探る。
第1節 ヘーゲルとの対立——体系と生成の分岐点
シェリングとヘーゲルは、ともにドイツ観念論の中核を成したが、その哲学的出発点からして決定的な違いがある。
ヘーゲルが〈絶対精神〉の自己展開を通じて全体の体系性を追求したのに対し、シェリングはむしろ、体系化が可能になる以前の「生成」そのものに関心を向けた。彼にとって「神」は、完全な全体ではなく、未だ完成されざるもの、無から立ち上がる過程としての存在である。
シェリングは哲学を、閉じられた体系としてではなく、開かれた運動としての「生成神学」に向かわせた。そこには、「神とは何か」という問い以上に、「神はどのようにして存在しうるのか」という根源的問いがある。
第2節 無と否定性の位置づけ——存在以前の深淵へ
シェリング後期哲学において、もっとも特異であり、かつ仮神論にとって示唆的なのは、「存在」ではなく「無」から哲学を始めるという態度である。彼は『存在の哲学』(Philosophie der Offenbarung)において、神とは何か以前に、「なぜ何かが存在するのか(=なぜ無ではないのか)」という問いを据えた。これはハイデガーの問いの先取りでもある。
ここでの「無」は単なる欠如や消極的状態ではない。むしろ、すべての可能性を孕んだ「積極的な深淵(der Abgrund)」であり、そこから神も世界も立ち上がってくる。「神」は最初から完成された存在ではなく、否定性の深みから自己を構成していく生成的プロセスとして捉えられるのだ。
この「否定性としての無」は、いわばあらゆる構造や秩序が現れる以前の、まだ意味が定まらない余地でもある。仮神論的に言えば、ここには「神を仮定する」ことが可能になる未規定の場=空白がある。
シェリング的「神」とは、既に在る存在者ではなく、「あらかじめ仮定される存在の根拠」である。
この視点から見ると、仮神とは、単に「いないもの」としての神ではなく、むしろ、「まだいないが、構造を可能にするもの」としての仮定――すなわち、「Axiom」に近づいていく。
この節が明らかにするのは、「無」や「否定性」が単なる絶望や消極ではなく、新たな倫理や構造を導き出す契機となりうるということだ。
第3節 生成される神——自然と自由の相互浸透
シェリング後期において特筆すべきは、神が「生成される」という考え方である。すなわち、神は完成された超越的実体としてではなく、生成の過程そのものとして理解される。ここでシェリングは、自由の哲学を通じて、「自然」と「自由」という本来は対立的な概念を、生成という一つの運動の中に統合しようと試みる。
この視点では、自然はもはや機械的・因果的な対象ではなく、自由の根源的現れとなる。自然は「非同一性の肯定」として働き、そこに人間の主体性や自由の可能性が根ざす。ここで登場するのが、彼の用語でいう「力としての原理」(Prinzip als Potenz)である。神はこの力の布置として、現実世界とともに生成していく構造そのものとなる。
言い換えれば、神は「既に存在する者」ではなく、「存在させようとする力の名」に他ならない。そしてこの力は、単なる物理的運動ではなく、倫理的・存在論的な緊張の場に生じる。
ここで仮神論は、シェリングの生成神学と響き合う。仮神とは、永遠の不在者でも、固定された絶対者でもなく、世界が自己を構成していく過程において、その中心に仮定される力の名前である。自然と自由、無と存在、否定性と構造性、これらの両極が緊張関係の中で織りなす場において、仮神は現れる。
このように、仮神は存在の背後にある原理ではなく、むしろ存在を生じさせる場において、自由の倫理として要請される仮定となる。シェリングにおいて、神は「生成される者」であり、そのことが仮神論における「Axiomとしての神」の着想につながっていく。
第4節 否定神学的汎神論への接続
シェリングの後期哲学において中心をなす概念のひとつが、「無底(Ungrund)」である。この語は直訳すれば「底なし」であり、存在の根拠そのものを欠いた、言語化不能な根源的否定性を表している。彼は、すべての存在や自然、さらには神そのものが、最終的にはこの「無底」から生まれると考えた。これは、存在をある意味で「不在」から生成させる神学的枠組みであり、否定神学と深く共鳴している。
否定神学(apophatic theology)は、神について「何かを言うこと」を禁じる神学である。神は無限であり、有限な言語では捉えられない。したがって神について語る最も正確な方法は、「神は何ではないか(non est)」と否定を積み重ねることにある。このアプローチは、神を沈黙と空白の彼方に置くことで、その絶対性を守ろうとする。シェリングはまさにこの否定の力を、「生成」の契機と捉えた。
興味深いのは、こうした否定神学的発想が、ある種の汎神論と結びつく点である。通常、汎神論は「すべてが神である」とする肯定的な世界観に見えるが、シェリングの場合、「神はすべての中にあるが、決して直接的には現れない」「すべてを貫通して在るが、それ自体としては掴めない」という否定性を保持した汎神論に至る。これは「否定神学的汎神論」と呼ぶにふさわしい立場であり、伝統的神学とも唯物論とも異なる第三の思考である。
このような枠組みは、現代において「仮神論(Hypo-theology)」という形で新たな展開を遂げうる。すなわち、神を「在る」と断言するのでも「無い」と否定するのでもなく、「仮にあるもの」として位置づける態度である。仮神論は、シェリングの「生成される神」「否定的な神」を継承しつつ、神を一種の“存在的条件”ではなく“思考の仮定”として再導入する営みである。
この節で示した否定神学的汎神論は、トポロジカルソサエティの設計原理において、「中心が空白であるがゆえに秩序が可能になる」という論理と深く結びついていく。次章では、この空白を構造化する思想としての「仮神論」の定義に踏み込んでいく。
第5節 仮神論の定義:〈神を仮定する〉という思考
仮神論(Hypo-theology)は、神を実体として信仰の対象に据えるのではなく、構造の条件として〈仮定する〉思想である。それは「神は存在する」あるいは「神は存在しない」といった判断のどちらをも退け、むしろ〈仮に存在するものとして扱う〉という中間的な立場を取る。この態度は、数学的思考における「公理(axiom)」の役割と驚くほど似ている。
数学において、公理は証明されることのない出発点である。例えば「任意の2点は1本の直線によって結ばれる」といった命題は、その真偽を問われるものではなく、「仮定される」ことで理論体系を支える。その意味で、仮神論における〈神〉とは、「存在する」と証明された対象ではなく、世界を理解し、構造化し、生きる上での〈思考の前提〉として機能する。神はaxiomであり、ある種の構造的必要性なのである。
ここで重要なのは、「仮定する」という態度が、単なる便宜的な想定にとどまらず、倫理的・文化的重みを持つという点である。神を仮定することによって、私たちは秩序や規範、意味や目的を一時的に与え直す。つまり、仮神論は「信じること」ではなく、「構造化すること」を通じて神の機能を呼び戻す。これは宗教の復興ではなく、むしろ宗教的構造の「再設計」である。
この立場はまた、「仮設された神(Hypothesized God)」という概念によって表現される。ここでの「仮設」は、可変性と限定性を内包する。それは絶対者ではなく、むしろ「仮に置かれる者」としての神である。数学が複数の公理系を許容するように、仮神論もまた複数の〈仮神〉を可能とする。重要なのは、「仮定があるからこそ、構造が立ち上がる」ということだ。
この意味で、仮神論は構造主義の言語論的発想を継承しつつも、それを一歩先へと進める。「語り得ぬものを語る」のではなく、「語り得ぬものを仮定する」。この非宗教的神学は、不在を前提とすることで、逆説的に社会や倫理の基盤を再構築しようとするものである。
次章では、こうした仮神論の思想をトポロジカルソサエティの設計原理へと接続し、「空白を中心に持つ共同体」の可能性を探っていく。
第II部 欠如の構造学——否定神学と仮神論
第4章 〈大他者の不在〉と象徴秩序——構造主義的視点の再考
第1節 象徴秩序とは何か——ラカンとレヴィ=ストロースの交点
20世紀思想における構造主義の核心は、目に見えない秩序の存在を前提とし、個別の表象の背後に共通の構造を見出す点にある。クロード・レヴィ=ストロースは神話や親族構造において普遍的な「構造」を明らかにし、ラカンはこの構造を人間の精神の形成にも適用した。ラカンにおける「象徴秩序(ordre symbolique)」とは、言語を介して主体を形成し、同時にその制約として働く枠組みである。
この象徴秩序の中核に置かれるのが「大他者(Autre)」である。大他者は単なる他人ではなく、法、規範、言語、文化といった象徴的な権威の総体である。それは私たちの語りや行為の背後にある「意味の保証者」として機能するが、実体として存在するわけではない。
この「存在しないのに存在するもの」としての〈大他者〉は、ラカンの思想において「他者は存在しない(l’Autre n’existe pas)」という命題に行き着く。つまり、私たちは常に意味の支えを他者に仮託しているが、その支え自体は幻想である。ここに〈欠如(manque)〉の構造が生まれる。
仮神論はまさにこの構造に立脚している。大他者の不在、すなわち「神の不在」を否定するのではなく、それを仮定として引き受けるのである。否定神学が神の語り得なさを強調したように、仮神論もまた「語れないもの」を前提に構造を構築しようとする。
第2節 〈神の不在〉をどう思考するか——構造主義と否定神学の架橋
構造主義の眼差しは、個人の意識や経験を超えた「背後の構造」に向けられていた。レヴィ=ストロースにおいては神話体系、フーコーにおいては言説編成、アルチュセールにおいてはイデオロギー、ラカンにおいては象徴秩序——いずれも、〈見えない秩序〉が人間の思考と行動を規定するという視点を共有している。
しかしこの見えない秩序は、「神」のような権威ある存在に似ている一方で、決して神ではない。というのも、それは〈意味の中心〉のように振る舞いながら、実際には中心を持たない非在の構造だからである。たとえばラカンの「他者の不在」や、デリダの「差延(différance)」の概念において、中心は常にズレ続け、決して到達されることがない。
この「中心なき構造」は、否定神学の思想と深く響き合う。否定神学において神は、「在る」とも「無い」とも言えない。存在や属性をすべて剥ぎ取られた神は、まさに〈語り得ぬもの〉として現前する。すなわち、「神は存在しない」という言明は、単なる無神論ではなく、より深い次元で神を捉えようとする神学的試みである。
仮神論が構想するのは、まさにこの「語り得ぬ神」を構造に仮置きすることによって、共同体や倫理の枠組みを構築する道である。これは、神を信じることによる救済ではなく、「神がいない」という前提の上に、神の“役割”を引き受ける概念を仮設的に導入する営みである。
このときに鍵となるのが、「仮設された神」としての〈Axiom〉である。Axiomとは数学における出発点——証明不可能だが前提とされる命題である。神が axiomatic であるという思想は、神の存在を証明しようとする伝統から離れ、「信仰」ではなく「構成」のための前提として神を用いるという態度を導く。
仮神論は、神を metaphysical な存在ではなく、epistemological な必要性として捉える。その際の神は、存在するか否かではなく、〈欠如の場所を保証するもの〉として構造の核に置かれる。このような神のあり方は、否定神学と構造主義の橋渡しとして、また新たな社会設計の理論的基盤として、重要な役割を果たすだろう。
第3節 ラカンにおける〈他者の不在〉と倫理
ジャック・ラカンの精神分析理論において、〈他者〉(l’Autre)は単なる他人を指すのではなく、言語、法、文化といった象徴秩序全体を意味している。個人はこの象徴秩序に取り込まれることで主観を形成するが、その象徴秩序は決して「完全なもの」として現れるわけではない。むしろラカンは、〈大他者は存在しない〉(Il n’y a pas de Grand Autre)という衝撃的な命題を掲げる。
この命題は、社会的秩序や倫理の背後にある「超越的な保証者」は不在であるという事実を示す。しかし同時に、私たちはそのような保証者が「いるかのように」振る舞わざるをえない。ラカンはこの構造を「シニフィアンの連鎖」における〈欠如〉と捉え、それが欲望の動因となると説く。
ここで重要なのは、倫理がもはや「絶対的な基準に従うこと」ではなく、〈他者の不在〉を引き受けた上で、いかに行為しうるかにシフトする点である。ラカンにとって倫理とは、「欲望に忠実であること」であり、これは「与えられた秩序への服従」ではない。むしろ、不完全で、裂け目を持った象徴秩序のなかで、それでも自らの選択を引き受けるという姿勢なのである。
仮神論は、このラカン的倫理をさらに拡張する。〈神は存在しない〉という前提を引き受けたうえで、なおその「神の役割」を誰か(あるいは何か)が担うことの倫理的意味を問う。このとき神は、信仰の対象ではなく、構造的な「欠如の名」のようなものとして仮定される。
そして、ラカンのいう〈他者の不在〉が人間の倫理を駆動するならば、仮神論における〈仮設された神〉=〈Axiom〉もまた、構造のなかで倫理的選択を可能にする条件となる。これは宗教的救済を目指すのではなく、不在を前提とすることで、自由と責任とを同時に立ち上げる道である。
このように、仮神論における神とは、「ある」とも「ない」とも言えぬものではなく、「ない」ことを出発点としたうえで、構造と倫理の条件として「仮定される」存在である。それは「信じられる神」ではなく、「機能する神」、すなわち制度や共同体が成り立つための〈空白の支点〉なのだ。
第4節 現代思想と否定神学の交差点
否定神学(アポファティック・シオロジー)は、神の本質を「言い表せないもの」として扱う伝統に属する。ディオニュシオス・アレオパギテス以来、この系譜は神を「存在する」とすら言わず、むしろ「神は存在を超えている」「神は存在しない」と言う。つまり神の否定を通じて、その超越性を指し示すのである。
現代思想において、この否定神学の方法は新たな意味をもって復活している。とくにハイデガー、デリダ、ナンシー、アガンベン、バディウらの思索には、否定神学の反響が強く見られる。彼らはそれぞれの形で「根源的な空白」や「不在の力」を中心に据え、そこから倫理、政治、存在を再構成しようとしてきた。
たとえばデリダは、「不在の痕跡」(trace)の思想において、意味とは常に遅延し、決して完結しないと述べる。この思想は神を明示的に扱うものではないが、あらゆる基盤の「脱構築」がもたらす構造的欠如を明らかにする。これは否定神学の「言えぬものへの沈黙」と響き合っている。
また、ナンシーの「無神論的キリスト教(atheological Christianity)」という概念は、神の死を超えて、それでもなお共同性や意味が立ち上がる可能性を問う。ここでは神はもはや超越的な存在ではないが、その「不在」がなお、私たちの関係性の条件として作用し続けている。
こうした現代思想の流れにおいて、否定神学はもはや単なる宗教的技法ではない。それは、いかなる「中心」も保証されない世界において、倫理と構造を再起動するための根源的な装置となっている。仮神論はまさにこの地点から出発する——〈不在の神〉を仮定し、その仮定の上に社会的構造や倫理的実践を築く試みである。
否定神学が「神について語らないこと」で神を指し示すように、仮神論は「神を信じないこと」で神の位置を構造的に演出する。そしてこの〈神の位置〉は、制度や共同体の構造を可能にする空白=Axiomとして機能するのだ。
第5章 否定神学と汎神論の結合——不在なる神の構造
第1節 否定神学と汎神論の一見する対立
否定神学と汎神論は、通常は対照的な神学的立場として分類される。前者は神を語ることを拒否し、沈黙によってその超越性を示す。一方、後者は万物に神が宿ると主張し、自然のあらゆる現象に神性を見出す。言語の否定と、世界の肯定。この二つは相容れないようにも見える。
しかし、両者にはある共通点が存在する。それは「人格神」を否定するという点においてである。否定神学の神は「何ものでもない者(Nothing)」であり、汎神論の神は「すべてなる者(Everything)」である。どちらも、キリスト教的伝統における人格的神とは異なる概念であり、その意味で神の〈場所〉を空白として捉え直す。
この章では、この二つの視点を対立ではなく構造的補完関係として再構成し、仮神論の中核にある「不在なる神」の構造的意義を明らかにしていく。
第2節 スピノザと現代における汎神論の再評価
スピノザは「神または自然(Deus sive Natura)」という有名な言葉において、神と自然を同一視した。彼の神は、人格をもたず、意志ももたず、祈っても応えない。だがその神は、世界そのものの論理的構造、すなわち必然性と秩序の別名でもある。
このような汎神論的神概念は、19世紀以降長く誤解と批判の対象となってきたが、現代において再び注目されている。その背景には、以下のような転換がある:
- 神の喪失後の神学:神の死以後、宗教の意義は道徳や共同体の形成に移行した。そこでは、スピノザ的な神が「価値と秩序の基盤」として静かに復権し始める。
- 自然科学との接続:ビッグバン、量子論、生態系ネットワークなど、自然そのものが「無限性」や「創造性」を帯びて語られるようになり、スピノザ的思考が再解釈される土壌が整ってきた。
- 政治哲学における影響:ネグリ、ドゥルーズらによって、スピノザの汎神論が集合的主体の理論、あるいはポストヒューマン的倫理の根拠として読み替えられた。
スピノザにおいて、神は「原因において無限なるもの(causa sui)」として世界の論理的前提である。まさにこの点において、仮神論における神=Axiom(仮設)という構造と接続が可能となる。
スピノザの神は信仰の対象ではなく、思考の出発点である。そしてそれは、神を「存在するか否か」ではなく、「前提として立てるべきか否か」という問いに転換する仮神論の基礎を準備するものでもある。
第3節 否定と充満の統合:空白の中の全体性
否定神学において、神は語り得ないもの、存在の彼方にある「空白」として現れる。この否定性は一見すると「無」を意味するかのようだが、むしろそれは満たされた空白、すなわちあらゆる意味づけが不可能であるがゆえに、逆説的に無限の可能性を含む場所として捉えられる。
この視点は、シェリングの生成神学における「始原的無」とも重なる。そこでは、「無」は空虚ではなく、未分化であるがゆえにすべてを孕んでいる。否定は単なる拒絶ではなく、「決定されざるものとしての豊かさ」なのである。
ここで重要なのは、「空白=否定」ではないということだ。否定性とは、あらゆる肯定を拒否するという意味において、むしろ全体性を包含する。その構造は以下のように整理できる:
- 肯定の神(人格神、創造神):限定された、意味づけされた存在。
- 否定の神(否定神学的神):語り得ないがゆえに、あらゆる可能性を超越的に内包する。
この「否定と充満の統合」は、仮神論において重要な基礎をなす。仮神とは、空白としての神、語ることができないがゆえに、その周囲に共同体を形成する中心点(center of gravity)である。
この考え方は、古代における神殿の「至聖所」の構造にも似ている。そこには像もなく、言葉もない——ただ空虚な空間があり、人々はその空白をめぐって儀礼と秩序を形成した。
仮神論はこの構造を引き継ぐ。空白の中に全体性を仮定し、それに応じて社会の構造を設計する。ここで神は信仰の対象ではなく、制度と倫理を成立させるための、否定性に基づく構造仮定となる。
第4節 仮神論の定式化:Axiomとしての神
仮神論の核心にあるのは、「神を信じる」のでも「神を否定する」のでもなく、神を仮定するという第三の態度である。この仮定は、数学における公理(axiom)の概念と深く結びついている。
公理とは、証明の必要がなく、体系全体を支える「前提」である。数学者がある理論体系を立ち上げる際、選ばれる公理のセットが異なれば、その上に築かれる理論も異なる。つまり、公理は真理の「源」ではなく、構造を成立させるための任意的な始点である。
仮神論において、「神」はまさにこの構造的公理(structural axiom)として理解される。信仰の対象ではなく、むしろ制度、倫理、象徴秩序を構築するための仮設された空白——それが神の役割である。
この意味で、仮神とは次のように定義される:
仮神とは、語りえぬ空白としての神であり、制度的秩序や倫理構造を支えるために仮設された axiomatic な存在である。
この発想は神学にとどまらない。たとえば国家、法、通貨、家族といった社会的制度の多くも、「それを信じること」ではなく、「それが仮に存在しているとすること」で機能している。これらもまた、仮神的構造といえる。
また、ここで導入された「axiomとしての神」は、今後の議論において特に重要になる。なぜなら、トポロジカルソサエティとは、この axiomatic な空白を中心に据えた構造的社会設計の試みだからである。
仮神論は、神の有無という二項対立から離れ、「前提とされる神」「制度を支える空白」として、神の新しい地位を提案する。それは脱宗教化の果てに、倫理や共同体の基盤を再構成する試みでもある。
第6章 仮神論の定義:〈神を仮定する〉という思考
第1節 〈不在〉から始まる理論構築
仮神論の中心的な命題は、「神は存在する」のでも「存在しない」のでもなく、「仮定される」という第三の形式である。ここで言う〈仮定〉は、数学における公理(Axiom)のようなものである。すなわち、それは証明されることなく、全体の構造を支える基底として想定される。
この観点から、仮神論における「神」は存在の対象ではなく、構造の条件である。神はあくまでも空白であり、欠如であり、しかしその不在が前提されることで象徴秩序や社会的構造が成り立つという逆説的機能を果たす。
ここで「仮設された神(Hypothetical God)」という概念が登場する。これは神を信仰の対象とするのではなく、社会や倫理の構造を立ち上げるための起点として仮置きするというラディカルな態度である。
第2節 「Axiom」としての神——構造の支点としての不在
この仮設的神の考え方は、まさに数学的公理(axiom)との類比によって理解できる。公理は自己証明も他者証明もされないが、あらゆる証明がそこから出発する基礎である。それは「真である」こと以上に「機能する」ことが重要であり、世界や言語、社会を動かすための条件として置かれる。
仮神論では、神は「真理」や「絶対者」としてではなく、欠如の場所(the locus of lack)として構造を支える装置とみなされる。フロイトにおける「原父」や、ラカンの「〈大他者〉の不在」といった概念とも接続されるが、仮神論はそこに倫理的・政治的意味づけを施す。
それは、「誰もがその不在を知りながら、それでもなお秩序が成り立つ」ような社会、すなわちトポロジカルソサエティの思想的基盤となる。
第3節 否定神学から仮神論へ——超越の喪失と倫理の転位
伝統的な否定神学(apophatic theology)は、「神は何であるか」ではなく「神は何ではないか」という否定の積み重ねによって、神の不可知性や超越性を際立たせてきた。ここで語られる神は、決して把握されず、いかなる概念にも回収されない超越的な空白として現れる。
仮神論は、この否定神学の系譜を引き継ぎつつ、そこから一歩踏み出す。神を「認識の彼方にある実在」としてではなく、「制度や秩序の基盤として機能する構造上の空白」として位置づけるのだ。
言い換えれば、否定神学が「神は存在しないことを通じて存在する」とするなら、仮神論は「神は仮定されることを通じて構造を可能にする」と述べる。この転位は、神の超越性を保持しつつ、具体的な社会的・倫理的実践と接続する道を開く。
仮神は、すべての人が「信じていない」ことを了解しつつ、それでも「その不在が共有されている」存在である。その意味で仮神とは、倫理的空白の公共的受容であり、信仰の代わりに構造を生きるという選択なのだ。
第4節 仮設された神という構造——Axiomとしての神の概念
ここで、仮神論の核心的アイデアである「神を仮定する」という構造を、数学的な比喩を用いてさらに明確にしよう。数学における公理(axiom)とは、証明されるものではなく、他の命題を導くために仮設として置かれる出発点である。それ自体は無根拠でありながら、全体の体系にとって決定的な役割を果たす。
仮神論における「神」もまた、このaxiom的な存在として捉えられる。すなわち、「この社会が成立するには神が存在すると仮定してみよう」という操作である。だが重要なのは、この神が実在する必要はないという点である。むしろ、誰も信じていない神が、社会構造の根を成すという逆説が、仮神論の根幹にある。
ここでの仮定は、単なる便利なフィクションではない。それは不在そのものを構造に織り込むという思想的実験であり、「空白」を中心に据える設計論である。神が存在することを前提にするのではなく、神が「仮設された存在」であることを前提にした秩序の可能性を問う。
この意味で、仮神は「信じるべき存在」ではなく、「前提として生きられる存在」である。まさにその点において、仮神は「axiom」として機能する。これは、宗教的信仰とは異なる倫理の地平を開く——信仰なき構造、権威なき秩序、それが仮神論が提示する社会設計の原理なのである。
第5節 言語・象徴・構造と〈神〉——記号的空白の中心
神が「存在」から「仮定」へと位置づけを変えるとき、それは単に宗教的意味の再解釈ではなく、象徴秩序そのものの構成原理の再設計を意味する。ここで問われるのは、神が「何であるか」ではなく、「神という記号が構造の中でどのように働いているか」である。
構造主義的視点から見れば、言語とは差異の体系であり、その中における「神」という語も、単独で意味を持つものではない。むしろ神は、象徴のネットワーク全体を支える空白の中心として機能する。ラカンが〈大他者〉に見たように、語る者たちの背後に、常に「意味を保証するはずの場所」があるという前提。だがその場所には、実体は存在しない。
この不在の場所——構造の中心でありながら欠如そのものであるもの——こそが、仮神の立ち位置である。仮神論における神は、語り得ぬ記号でありながら、その不在ゆえに構造が成立するというパラドックスを体現している。
ここで〈神〉は、社会や倫理の「正しさ」を保証する存在ではなく、むしろ、「正しさが保証されない」ということを皆が了解しながら、それでも共有しうる象徴的空白の中心となる。仮神とは、言語的・社会的秩序を支える「ありもしない保証者」でありながら、その「ありもしなさ」自体が機能するという、きわめてラディカルな構造的仮設である。
第6節 仮神をめぐる倫理——信仰なき秩序の可能性
仮神論が私たちに問いかけるのは、「神がいない世界で、私たちはどう生きるか」という根本的な倫理の問題である。これは単なる宗教の否定ではなく、神なき時代においてもなお〈神の機能〉が必要であるという認識から出発している。
ここでの神は、「救済」や「真理」を与える存在ではない。むしろ、人々が生きるうえで拠りどころとせざるをえない構造の〈空白の支点〉である。重要なのは、それが信仰を前提としないという点である。仮神論が提示するのは、「誰も信じていないのに、それでも機能する神」という倫理的逆説なのだ。
この逆説のなかで、私たちは新たな責任を引き受けることになる。つまり、かつては「神が命じた」とされたことを、今では「私たち自身が選び取る」しかない。だからこそ、仮神とは倫理の再定義でもある。信仰ではなく、構造と選択に基づいた倫理。それが仮神論の最終的な意味である。
この倫理は、単に個人の内面の問題ではない。それは、共同体の構造そのものにかかわる問いであり、トポロジカルソサエティの設計原理として今後展開されることになる。「神を仮定すること」は、「私たちはこの空白を共有する」という合意であり、信仰の共同体ではなく、欠如を共有する共同体としての倫理的提案なのである。
第III部 トポロジカルソサエティの設計
第7章 トポロジー的比喩と構造思考——開かれた場の設計
第1節 トポロジーとは何か——連続性と変形の思想
トポロジー(位相幾何学)は、幾何学の一分野でありながら、長さや角度といった量的性質ではなく、「連続性」「境界」「穴」などの構造的特徴の保たれ方に関心を持つ分野である。たとえば、円と楕円、マグカップとドーナツは、連続変形可能である限り、トポロジー的には同じ「位相空間」に属するとされる。
この「形が変わっても、構造が保たれる」という考え方は、社会や思想における構造の理解に深く貢献しうる。とりわけ、神の不在を前提とした仮神論において、「固定された中心」ではなく、「変形可能な構造の秩序」として社会を再構築する視点が必要となる。
ここで導入されるのが、「トポロジカルソサエティ」という構想である。それは、不可視の空白=仮神を中心に据えながらも、柔軟で、相互に連続し、分裂や断絶すら組み込むことのできる社会構造の設計原理を模索するものである。
第2節 比喩としての“穴”——欠如の構造と包摂の空間
トポロジーのもっとも象徴的なモチーフのひとつが「穴」である。円環、ドーナツ、トーラス、メビウスの帯など、これらの図形が保持している本質は、まさに「欠如」の存在である。完全な閉域ではなく、抜け落ちた空間=中心の不在を抱えた構造が、トポロジー的に特異な意味を持つ。
仮神論が提示する〈仮設された神〉とは、この「穴」と非常に近い構造を持つ。神はもはや世界の中心に存在していない。しかし、その不在が共有されることで、周囲の構造が秩序を保つ。穴とは、そこに「何かがある」から意味が生まれるのではなく、「何かがない」ということによって全体の構成が成り立つという逆説的装置である。
社会においても、ある中心的価値や権威が「実体として」存在するわけではない。それでも、人びとはその「あるべきもの」「かつてあったもの」「仮にあるとされるもの」をめぐって秩序を形成する。これは、記号論的に言えば「空白の記号」、トポロジー的に言えば「穴のある空間」の中で意味がめぐるということに他ならない。
トポロジカルソサエティは、この「欠如を中心に持つ構造」として設計されるべきだ。そこでは、穴を消すことも、埋めることもせず、むしろその穴を包み込み、動的秩序を生み出すような構造=倫理が求められる。
第3節 閉じられた中心ではなく、開かれた縁を——場としての社会構造
近代社会の構想はしばしば「中心」を前提としていた。国家、法、宗教、家族といった制度は、いずれも〈上位の価値〉や〈権威の核〉を想定することで秩序を保とうとしてきた。しかしこの構造は、「中心が崩れる」ことで簡単に瓦解するという脆弱さを抱えている。
仮神論はこの前提を根本から転換する。中心を実体化せず、むしろ中心の不在(=仮設された神)を前提とする社会構造を構想する。それは、権威の集中ではなく、縁=周縁の連続性や関係性に重きを置くネットワーク的社会である。
ここでトポロジー的思考が活きてくる。トポロジーにおいては、物の形ではなく、その連続性とつながりの在り方こそが本質である。つまり、「場」や「縁」が変化しても、構造が維持されることに価値がある。これは、単一の中心から全体を組織する発想とはまったく異なる。
トポロジカルソサエティとは、あらかじめ定まった中心を持たず、周縁が変動し続けることで柔軟性を保つ社会である。そこでは、人びとは「何を信じるか」ではなく、「どのような欠如を共有するか」によって連帯する。倫理は中心から命じられるのではなく、境界=縁からにじみ出るようにして生まれてくる。
このように、仮神論が提案する社会構造とは、「空白を中心に据えたトポロジカルな場」なのである。次章では、その空白をどのように実際の共同体デザインに組み込むかを検討していく。
第8章 〈空白〉を中心とする共同体デザイン
第1節 権威の脱中心化と象徴的空白
仮神論において「神」は実在ではない。だが、それでもなお必要とされる。なぜなら、構造や共同体が成立するためには、**人々が共有できる「中心」——あるいはその「空白」——が不可欠だからである。ここで私たちは、〈空白〉を前提とした社会設計、すなわち「仮神的秩序」の実装に向けて考察を進める。
現代社会では、かつての宗教的・国家的・家父長的権威の崩壊によって、中心の象徴的機能が空洞化している。しかしその空洞を単に否定的に受け止めるのではなく、創造的な構造の出発点として引き受けることができるのではないか?——これが仮神論的共同体の基本発想である。
この共同体において、中心とは「集権」ではなく「構造的な欠如」である。それは統治や支配の原点ではなく、むしろ誰も占有しえない“空”の位置として共同体全体を支える「機能的空白」である。ちょうど、古代神殿の「至聖所」や、王権における「空位(interregnum)」、または能における「間(ま)」が象徴的な空白として機能するように。
この〈空白〉は、全員が仮に承認することで初めて機能する。つまり、それは実在ではなく、構造的フィクションとしての神=仮神である。これが制度の中に、強制ではなく共有によって秩序を立ち上げる仕組みを生み出す。
第2節 空白をめぐる合意——信じない者たちの共同性
仮神論的共同体において、共有されるのは「信仰」ではない。むしろ、それは「神が不在であることを了解した人びとが、なおその“場所”を仮定することに合意する」というパラドックスに基づいている。言い換えれば、それは〈空白〉をめぐる合意である。
このとき「神」は、誰も実体的には信じていないが、その欠如を共有することで関係を形成するという存在となる。ここでの神は、まるで舞台上の空席、あるいは空の椅子のようなものだ。その空席を巡って人々が輪になって座り、「誰もそこにいない」ことを知りながら、なお秩序が生まれてくる。
この構造には、次のような倫理的意味がある:
- 誰も中心に立たない(=権威の集中を防ぐ)
- 誰もが中心を囲む(=平等な関与)
- 空白を保持する(=制度の柔軟性と持続性)
仮神とは、まさにこの空白の椅子のようなものである。その不在によって、共同性が成り立つという逆説的機能を果たす。これは、「信仰を持つ者たち」ではなく、「信じないことを了解し、それでも合意しうる者たち」の共同体である。
このような秩序の在り方は、従来の国家・宗教・イデオロギーに基づく共同性とは大きく異なる。そこでは、共通の正義や神話ではなく、共通の〈欠如〉とその構造的合意が、人びとを結びつけるのである。
第3節 制度設計としての“仮神”——柔軟な秩序の原理
これまで見てきたように、仮神論は「神の不在」を前提としつつも、それを構造の支点として積極的に再構成しようとする思想である。そのもっとも現実的な応用の場が、制度設計である。ここでは、「仮神」を組織・社会・共同体の制度的中核として仮定することが、どのような秩序を可能にするかを考察する。
従来の制度は、正統性の根拠を何らかの超越的権威(神、法、伝統、人民、歴史など)に依存してきた。しかし現代において、それらの権威はことごとく相対化され、時には機能不全に陥っている。ここで求められるのは、絶対性なき秩序=信仰なき正統性の構築である。
仮神を制度の中心に仮定することで、次のような構造的効果が生まれる:
- 中心の空白化
→ 誰も占有しない中心を設けることで、権威の集中を防ぐ。 - 構造の柔軟化
→ 仮設された神は可変的であり、社会状況に応じて再構成が可能。 - 責任の共有化
→ 中心の不在によって、責任や判断は共同体全体に分散される。
こうした設計思想は、形式的なルールではなく、「欠如を共有すること」そのものを制度化するという新たな秩序原理となる。たとえば議事運営における「空席の司会者」や、「絶対に使われない議長権限」など、構造的空白を制度の一部として組み込むことで、組織の柔軟性と倫理的自律性を保つことができる。
つまり、仮神とは「統治する者」ではなく、「誰もがその不在に向かって思考するための場所」なのである。これは、硬直した制度の時代から、自己更新可能な構造へと移行するための思想的プロトタイプである。
第9章 仮神を中心に据える社会構造——権威なき秩序の生成
第1節 神なき社会から、仮神の社会へ
現代社会は、あらゆる「絶対的なもの」の崩壊を経験した時代である。宗教的神、国家の正統性、家族の権威、科学の客観性——いずれももはや自明な中心ではありえない。しかしそれでもなお、私たちは秩序を必要としている。しかもそれは、もはや上から与えられるものではなく、不在を前提に構築される秩序でなければならない。
ここで登場するのが、「仮神を中心に据える社会構造」である。
仮神は、信仰される対象ではなく、制度や倫理を編成する“空白の核”として機能する。誰も占有しない、だが皆が了解する。そこには、かつての「権威」のような実体はない。あるのは、不在が合意されているという了解である。
この構造の強みは、権威なきままに秩序が成立するという点にある。それは、ラディカルな相互承認による秩序、欠如をめぐる共感によって保たれる共同体、そして自由と責任を同時に引き受ける構造である。
第2節 非主権的秩序としてのトポロジカルソサエティ
近代国家の秩序モデルは、基本的に「主権(sovereignty)」の論理に支えられていた。そこでは、ある一者(君主、法、人民)が最終的な決定権を握ることで、秩序の正統性と安定性を担保していた。しかしこの主権モデルは、決定者不在の状態や、流動的な価値観の中では脆弱である。加えて、主権の集中は抑圧や排除と隣り合わせにもなりやすい。
仮神論に基づくトポロジカルソサエティは、この主権モデルとはまったく異なる秩序の形を目指す。それは「非主権的秩序」、つまり最終決定者なき構造である。だが無秩序ではない。むしろ、〈空白の中心〉を仮定することで、秩序を持続的に再編成できる構造を生み出す。
この社会では、「神(=仮神)」が最終的な正統性の源ではない。むしろ、その「不在が可視化されている」という了解が、秩序の条件となる。トポロジカルに言えば、それは「中央が穴である構造」「中心が常に空いている制度」として設計される。
この非主権的な秩序では、次のような特性が生じる:
- 権威は流動的である(中心に定着せず、更新される)
- 判断は分散される(誰もが部分的に構造を担う)
- 失敗は吸収される(空白が再編の余地を保証する)
つまり、トポロジカルソサエティとは「絶対者なきままに成立する秩序の形」であり、その論理は主権や権威とは別の軸——欠如・関係性・合意——を中心にしている。
第3節 権威の空白が生む創造——制度と倫理の接続
仮神論の核心は、「神がいない」ということを否定でも悲観でもなく、構造的前提として受け入れることである。そしてその不在が、「秩序をつくる意志」を個々人の内に呼び起こす。すなわち、権威の空白が倫理の起点となるのだ。
従来、倫理とは多くの場合「上から与えられるもの」として機能してきた。宗教においては神が、国家においては法が、個人の行為を規定していた。しかし仮神論が指し示すのは、上から与えられる倫理ではなく、自ら引き受ける倫理である。それは、空白の中に秩序を立ち上げるという、創造的かつ責任的な営みである。
このとき制度とは、硬直したルールの集合ではなく、不在を内包しつつ可変的に展開する「場」となる。誰かが絶対的に決定するのではなく、誰もが空白を見つめながら、「どのような秩序を共有するか」を継続的に問い直す。これが仮神的構造の持つ動的特性である。
このような制度は、「神の命令を守る」という旧来的な宗教倫理とは異なり、「神がいない世界で、なお秩序をつくる」という倫理的実践を要求する。そこでは、構造と倫理が分かちがたく結びつき、構造化することそのものが倫理となる。
だからこそ、トポロジカルソサエティは単なる思想的図式ではなく、構造と倫理の接点において生成される社会モデルであり、仮神論はその原理的基盤となる。
第IV部 エトマスとの接続——数学することは、生きること
第10章 クロネッカー、ニーチェ、そして自然数の構成問題
第1節 「神は整数をつくった」——クロネッカーの信仰
19世紀の数学者レオポルト・クロネッカーは、「神は整数をつくった。他のすべては人間の仕事である(Die ganzen Zahlen hat der liebe Gott gemacht, alles andere ist Menschenwerk)」という言葉を残した。これは一見すると、整数の“自然性”や“絶対性”を讃えるように聞こえるが、実はそこには深い哲学的・神学的問いが隠されている。
クロネッカーは、「自然数」は人間の構築物ではなく、宇宙の根底に与えられたもの(=神の創造)であると信じた。だが、ニーチェ以後の時代において、この信仰はもはや維持されえない。神が死んだとき、私たちは自然数をも“神なき世界”で構築せねばならないのだ。
この章は、クロネッカー的な整数観を出発点に、ニーチェの「神の死」と重ね合わせながら、「自然数とは何か」という根本的な問いを、仮神論的思考とエトジェネティック・マセマティクス(EthoMath)の接続に向けて展開していく。
第2節 神の死と自然数の根拠喪失
クロネッカーにとって、自然数は神によって与えられた絶対的存在であった。だが、ニーチェが「神は死んだ」と宣告したとき、その言葉は宗教的な信仰だけでなく、絶対的な根拠の時代の終焉を意味していた。自然数もまた例外ではない。もはやそれは、宇宙にあらかじめ与えられた前提ではなくなった。
近代以降の数学は、数の定義を再構築する必要に迫られた。ペアノの公理系、フレーゲの論理主義、そして集合論的な定義——それらはいずれも、「自然数を“つくる”ための理論的な試み」だった。数は神から与えられたものではなく、人間が“構成する”ものになったのである。
しかしここに、ある根源的な不安が生じる。もしも数の根拠がもはや神ではないとすれば、どこにその確かさを求めればいいのか? 論理そのものの基盤もまた相対化された現代において、自然数を「信じる」ことさえ困難になっている。つまり、神の死は数学の内部にも〈根拠の喪失〉という形で浸透しているのだ。
仮神論の観点から言えば、ここで問われるのは、神なき時代において、どのようにして自然数を仮定し、構造を立ち上げるかという倫理的な問題である。数は信仰の対象ではなくなった。だが、それでもなお私たちは「数を使って生きる」必要がある。そのとき、数を何に依拠して仮定するのか? この問いは、数学の問題であると同時に、生の問題でもある。
第3節 仮神としての自然数——エトマスの構想
自然数はもはや「神が与えた真理」ではなくなった。しかし、それでも私たちは自然数を使い、そこから世界を測り、考え、生きている。ここにこそ、仮神論とエトジェネティック・マセマティクス(EthoMath)の接点がある。
エトマスは、数学を単なる論理的操作ではなく、生きられる構造=存在の形式として捉える。その前提として重要なのが、自然数を「信仰の対象」としてではなく、「仮定される秩序」として扱うことだ。ここでの自然数は、まさに仮神のように、実体はないが機能するものとして制度化される。
この仮設的秩序としての数は、次のような特徴をもつ:
- 誰もその「起源」を知らないが、皆が共有している
- 証明されないが、構造を導く前提として使われる
- 倫理的態度として「選び取られる」
つまり、自然数は「真理」ではなく、「仮定された秩序」として、私たちの生に貫入している。これは、まさに仮神としての自然数という思想である。神が死んだ後も、私たちは数を手放せない。だからこそ、数を「仮定する」という行為そのものが、生きることの一形式=エトマス的倫理となる。
次章では、この構想をさらに深め、エトマス的数学の基本構造——「仮定される数/生きられる構造」について詳述する。
第11章 エトマス的数学——仮定される数・生きられる構造
第1節 エトジェネティック・マセマティクスの基本理念
「エトジェネティック・マセマティクス(EthoMath)」とは、数学を単なる形式的言語ではなく、生の実践に根ざした構造生成の運動として捉える思想体系である。ここで数学は、世界を記述する「言語」ではなく、むしろ世界を生きること自体が生成する「形」として現れる。
この立場において、数や構造は次のような特徴を持つ:
- 数は仮定される:自然数は公理的に「与えられる」のではなく、倫理的に「選び取られる」。
- 構造は生きられる:論理の演繹体系としてではなく、経験・行動・関係性の中に編み込まれていく。
- 数学は制度であると同時に、生活である:数えること、測ること、区切ること、比較することはすべて、人間の生活のなかで立ち上がる「生の構造化行為」なのである。
このような数学観は、20世紀的な論理主義や形式主義を乗り越え、構造そのものに倫理的厚みを与える。つまり、エトマスにおいて数学することは、「正しい答えを出すこと」ではなく、「どう生きるかを組み立てること」に他ならない。
第2節 形式ではなく関係——構造の倫理化
近代数学は、「形式」を重視してきた。集合論、論理体系、公理化の運動——それらはすべて、数学を「中身に依存しない抽象的構造」として捉える態度に立脚していた。だが、エトマスにおいて重要なのは、「何を前提とするか」ではなく、「どう関係を結ぶか」である。
ここでの構造とは、固定的な図式ではなく、生の中に絶えず生成・変化していく関係の網である。たとえば、数の操作一つをとっても、それは計算のための技法であると同時に、世界に働きかけ、自他を区別し、他者と接続するための実践である。
この視点では、以下のような転換が生じる:
| 従来の数学 | エトマス的数学 |
|---|---|
| 公理は絶対的前提 | 公理は仮設的選択(axiom=仮神) |
| 数は形式的対象 | 数は生きられる関係 |
| 構造は論理的体系 | 構造は倫理的選択の結果 |
構造は、ただ「ある」ものではなく、「生きられるもの」である。つまり、人びとが〈何を信じるか〉ではなく、〈何を仮定して、どう生きるか〉によって構造が立ち上がる。そのとき数学は、記号の遊びではなく、生の技法=エートスの表現として新たな意味を獲得する。
第3節 構造化することは生きること——数えることの倫理
エトマスの根本命題のひとつは、「数学することは、生きることである」という言葉に凝縮される。この命題は、単なる比喩ではない。むしろ、生きるという営みそのものが、すでに構造化=数学的実践であるという立場を示している。
私たちは日常的に数えている。時間を、距離を、言葉を、人間関係を——だがそれは単なる数量化ではない。数えるとは、違いをつくり、世界に意味を与えることである。だからこそ、「数える」ことは倫理と不可分なのだ。
たとえば、「誰を含め、誰を除外するのか?」という問いは、集合論の問題であると同時に、共同体の構成にかかわる倫理的判断でもある。「どこで区切るか」「何をひとつとみなすか」という数の操作には、他者への態度、責任、視線が組み込まれている。
仮神論における神が〈空白の中心〉として仮定されるように、エトマスにおける数もまた、〈正しさの根拠〉ではなく〈共に生きるための仮定〉として選び取られる。つまり、数えることは生きることのひとつのスタイルであり、構造をつくることは、同時に生き方を問うことなのである。
このとき、数学とは知の体系ではなく、存在の技術=エートスを支える実践となる。まさにそこにおいて、仮神論とエトマスは交差する。
——「信じられないものを、それでもなお仮定すること」こそが、倫理であり、構造であり、生そのものである。
第12章 欠如の上に立つ数学——倫理としての構造化
第1節 完全性ではなく、欠如を前提とする構造
現代数学の歴史は、「完全性」への希求と、それが不可能であるという認識とのあいだを揺れ動いてきた。ゲーデルの不完全性定理は、いかなる一貫した形式体系も、その内部で完全な自己証明を行えないことを示した。この衝撃的な結果は、数学を「絶対的な真理の体系」としてではなく、常に何かを欠いた構造として捉えることを強いた。
エトマスにおける数学は、この「欠如」をマイナスとしてではなく、構造を開くための条件として肯定する。つまり、完全な構造ではなく、「開かれた構造」「仮定に支えられた不安定な場」を倫理的に引き受けるのである。
ここで数学することは、閉じられた答えに到達することではない。むしろ、答えなき問いの形を整え、共に生きる構造を仮定することである。
第2節 数学と倫理の交差点——選び取られる構造
エトマスの視点から見ると、数学とはもはや「発見される真理」ではない。むしろそれは、構造をどう仮定するか、どの前提を生きるかという倫理的選択の営みである。ここで問われるのは、「何が正しいか」ではなく、「どのような構造を私たちは引き受けるのか」という姿勢である。
たとえば、平行線の公理を変えることでユークリッド幾何学が非ユークリッド幾何学へと変容したように、公理とは選び取られるものであり、その選択によって世界の見え方もまた変わる。そしてこの選択は、生き方の選択と不可分である。
- 自然数を仮定するとは、数の確かさを信じることではなく、数えることの意味を引き受けることである。
- 無限を導入するとは、世界を閉じられたものではなく、開かれた可能性として扱うことである。
- 欠如を受け入れるとは、不完全さに耐え、それでもなお構造を立ち上げる倫理を選ぶことである。
このように、数学は単なる論理体系ではなく、価値の前提であり、世界の構成法であり、他者との共生の技法となる。エトマス的数学とは、数学を通じて倫理を問う実践であり、それは仮神論の目指す社会設計とも深く共鳴する。
仮神論における「神の仮定」が倫理であるように、エトマスにおける「構造の仮定」もまた倫理である。信じるのではなく、仮定することによって私たちは秩序を立ち上げる。ここに、数学と生の交差点がある。
第3節 構造のうえに立つ責任——エトマスと仮神論の統合
ここに至って、エトジェネティック・マセマティクス(EthoMath)と仮神論は、ひとつの思想的交差点にたどり着く。それは、欠如を前提としながらも、それでもなお構造を仮定し、選び取り、生きていくという、倫理としての構造化の思想である。
仮神論が問いかけるのは、「神がいないことを前提にして、なお社会的秩序をどう築くか?」という問題である。エトマスが問いかけるのは、「真理が絶対でなくなった時代に、どのような構造を仮定して生きるか?」という問題である。
この二つの問いは、いずれも根拠の喪失を出発点としながら、創造的な秩序を立ち上げるという倫理的実践へと収束していく。
どちらも信仰に依存しない。
どちらも「空白を共有する」という選択に基づいている。
そしてどちらも、「選び取った構造に対して責任を持つ」ことを要求する。
これは、もはや知識の問題ではない。
それは、いかに生きるかという倫理の問題であり、いかに構造を共有しうるかという共同体の問題である。
仮神論とエトマスの統合は、宗教でも数学でもない。
それは、神のいない世界をなお生きるための構造的・倫理的な勇気の名前なのである。
終章 未来への設計図
第1節 神を信じないことではなく、仮定することで生まれる倫理
本書を通して繰り返されてきたのは、「信じるか、信じないか」という二項対立を超えた第三の選択肢——〈仮定する〉ことの思想である。
神がいないと知りながら、それでも神を仮定すること。
真理が確定できないと知りながら、それでも構造を選び取ること。
この「仮定としての倫理」こそが、仮神論の中核であり、エトマスの数学観とも深く響き合っている。
信仰の時代が終わり、すべての権威が相対化された今、私たちに求められているのは、不在を引き受ける勇気である。
その勇気こそが、共に構造を仮定し、空白をめぐって秩序を築くための出発点となる。
第2節 トポロジカルソサエティの実装可能性と文化的展望
仮神論とエトマスは、抽象的な思想にとどまらない。両者は、「不在を前提にした構造」がいかに社会の現場で機能しうるかという問いに向かっている。その応答として提示されるのが、トポロジカルソサエティ(位相的共同体)という新たな社会モデルである。
トポロジカルソサエティは、次のような原理に基づいて設計される:
- 中心を空白とし、それを共有することで秩序が成立する
- 固定された権威を持たず、変形可能な関係性を保つ
- 共通の信仰ではなく、共通の“欠如”を通じて連帯が生まれる
このような社会は、すでにいくつかの文化的実験や運動の中に予兆として現れている。
例えば、強固なリーダー不在のまま意思決定を行う水平的な自治モデル。
または、制度の正統性をあえて「空席」にすることで責任を共有する新しい政治実験。
さらには、教育や芸術の現場における「空白の中心」をめぐる創造的構造化の試み。
これらはいずれも、「誰かが導く社会」ではなく、「誰もが欠如に向き合う社会」の萌芽であり、仮神論的倫理の実装例ともいえる。
未来の社会に必要なのは、完璧な設計でもユートピアでもない。
それはむしろ、「空白を保持し続けることができる構造」であり、完成を拒む開かれた秩序なのだ。
第3節 不在を引き受ける勇気としての仮神論
本書の最初から最後まで貫かれてきたのは、「神の不在」という思想的地平に、否定ではなく創造によって応答するという態度であった。
私たちはもはや、「神がいる」という前提には戻れない。
しかし、「いない」ということに絶望する必要もない。
むしろその〈いなさ〉を共有し、仮定し、構造を築くことで、
新たな倫理と共同体の形を生きることができる。
仮神論とは、虚無を受け入れる思想ではない。
それは、不在を前提に、なおも世界を構築しようとする意志の哲学である。
そこに求められるのは、盲信でも懐疑でもなく、仮定することの勇気である。
この勇気は、数学にも通じる。
誰も自然数を「証明」していないが、それを仮定することで無限の構造が立ち上がる。
それと同じように、神を仮定することで、信仰なき倫理、権威なき秩序、
そして共に生きうる場が創造される。
不在を引き受けること。
欠如を仮定すること。
信じないことで終わらず、仮定することで生きること。
それが、仮神論であり、トポロジカルソサエティの出発点であり、
エトマスにおける「数学することは、生きること」の意味なのである。
参考文献一覧
フリードリヒ・シェリング『人間的自由の本質について』
ジャック・ラカン『無意識の倫理』
マルティン・ハイデガー『存在と時間』
ジャック・デリダ『声と現象』
クロード・レヴィ=ストロース『野生の思考』
ゲオルク・カントール『無限への寄与』
クルト・ゲーデル『形式的不可完全性定理』
東浩紀『一般意思2.0』
森田真生『数学する身体』
クロネッカー、ペアノ、フレーゲ各氏による数学基礎論関連文献
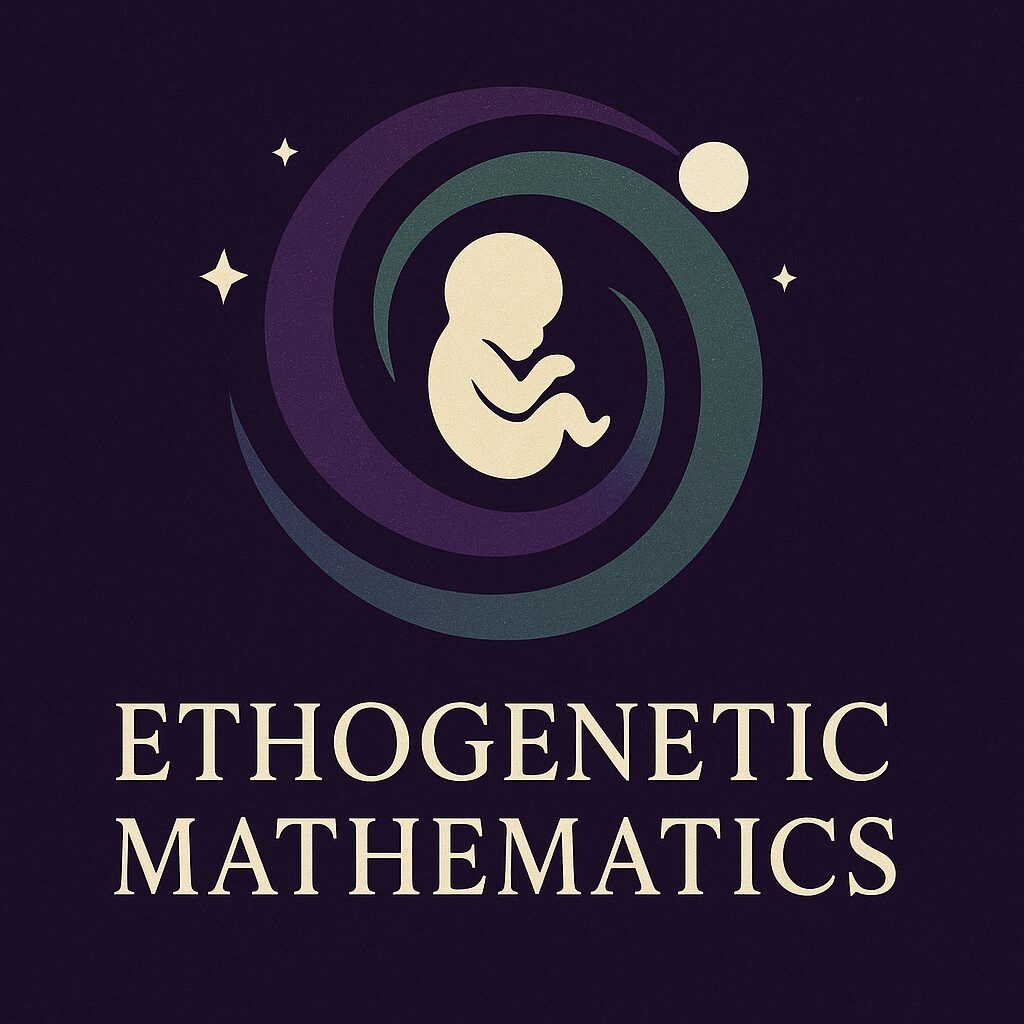


コメント