序章 しあわせとは、何なのでしょうか。
しあわせとは、何なのでしょうか。
それは、あまりにも多くの人が口にしながら、
本当のところでは、だれも答えられない問いのように思えます。
僕がこの問いに向き合うようになったのは、ごく最近のことではありません。
むしろ、気づかぬうちに、ずっと心の奥でその問いを繰り返してきたのだと思います。
子どもの頃の僕にとって、「しあわせ」なんて言葉は、
教室にも家庭にも存在していませんでした。
笑っているはずのときも、なぜか心がどこか遠くにいるような感覚がありました。
友達と遊びながらも、胸の奥には言いようのない“足りなさ”がありました。
それは名前を持たない欠如であり、誰にも伝えることのできない沈黙でした。
やがて僕は、数学に出会いました。
数式の中には、混乱を整理し、世界を秩序づける力があるように感じました。
バラバラだった世界に、一本の線が引かれるような心地がしたのです。
でも、どれだけ定理を証明しても、どれだけ構造を理解しても、
僕の内側には、ずっと“語れなかったもの”が残り続けていました。
その後、詩に出会いました。
詩は、正しさを持たないままに在る言葉です。
意味ではなく、響きによって、人の心に届くものです。
僕はそこで初めて、
「語りきれなさ」に寄り添うことが、ひとつの赦しになるのだと知りました。
数学と詩。
それは、まったく違う方法でありながら、
ともに“欠如”をめぐる営みであると、いまなら言えます。
どちらも、幸福という問いを避けることなく、
その周囲を、静かに、しかし決して見失わずに、巡り続けていたのです。
この本は、そうした営みの記録です。
ひとりの人間が、欠如とともに生き、
それでも幸福を語ろうとした、ささやかな試みです。
もし、あなたにもまだ言葉にならなかった“何か”があるのなら、
どうか、この本のいずれかの章が、
その沈黙にそっと触れることがありますように。
それを、僕は幸福と呼びたいのです。
第1章 秩序の外にいた少年――初めての欠如
⸻
小学生の頃の僕は、うまく生きられない子どもでした。
授業中に立ち歩いたり、先生に反抗したり、
自分の思い通りにならないと、すぐに怒鳴ったり暴れたりしました。
放課後は、同じように怒られ慣れた子たちとつるんで、
ときに他人を笑いものにし、ときにモノを壊し、
自分が傷つかないように、先に誰かを傷つけていました。
⸻
学校が嫌いでした。
でも、家もまた、あたたかい場所ではありませんでした。
両親はよく口論していて、僕が問題を起こすたびに、父の声が荒れました。
母の眉間のしわは、記憶の中でずっと残っています。
それでも僕は、毎日学校に行きました。
行かなければ、もっと怒られることがわかっていたからです。
⸻
唯一、誇りに近いものを感じていたのは、バスケットボールでした。
体格は小さかったけれど、走るのは速く、反射もよかった。
パスを回し、シュートを決める。
それが、まるで自分が「ここにいていい」と証明できる瞬間のようでした。
試合で勝つと、チームメイトの目が変わりました。
父も、そのときだけは「よくやったな」と声をかけてくれました。
だから、僕は必死に練習しました。
その言葉に、ようやく生きている実感があったからです。
⸻
でも、長くは続きませんでした。
スランプが来ました。
試合で空回りし、交代を告げられる。
それが何度か続いたあと、父が言いました。
「そんなに辛いなら、もう辞めてもいいんじゃないか?」
⸻
胸に穴が空いたような感覚でした。
僕は、辞めたいと思っていたはずでした。
練習はしんどくて、友達と遊ぶ時間もなかった。
それなのに、その一言が、どうしようもなく悔しかったのです。
父は、続けてこう言いました。
「お前が活躍できないのに頑張ってる姿を見る方が、こっちの方が辛い」
⸻
それは、優しさではなかったように思います。
僕にとっては、自分の存在が“誰かの目に耐えられないもの”だと言われたように聞こえました。
その夜、僕は本気で「死んでもいいかもしれない」と思いました。
布団の中で声も出せずに泣き、天井を見つめながら朝を待ちました。
けれど、何もできませんでした。
死ぬのが怖かったのではありません。
何をどう終わらせていいのか、まったくわからなかったのです。
⸻
それから少しして、偶然にも、皆既月食を目にする機会がありました。
月が、すこしずつ、地球の影に隠れていく。
そして、しばらくするとまた、何事もなかったように戻っていく。
その様子を、ただ黙って見つめているとき、
胸の中にひとつの確信が生まれました。
⸻
壊れていたのは、世界ではなかった。
壊れていたのは、僕だったのだと。
⸻
月は、黙って隠れ、そして戻る。
そこには、僕が求めていたような、崩れない秩序がありました。
その夜から、僕は夜空を見上げるようになりました。
図書館で星や天文学の本を借り、
宇宙の構造や重力、時間の話に夢中になっていきました。
⸻
世界には、回転するものがあり、軌道があり、
どんなに遠くても“つながっている”という感覚がありました。
それが、どれほど心を支えてくれたか、
今となっては言葉にするのが難しいくらいです。
⸻
そして、僕は心の中で、初めて小さくつぶやいたのです。
「世界はばらばらじゃない」と。
⸻
この言葉が、僕の中に構造を生み、
やがて「数学」と名づけられるものに出会う土壌となっていきました。
でもその話は、もう少し先の章に譲ることにします。
第2章 わかることの快感、赦されない自分
⸻
中学生になった僕は、相変わらず“良い子”ではありませんでした。
小学校の延長線のような日々を過ごし、不真面目な連中とつるんで、
廊下でふざけ、授業中に私語を重ね、何度も先生に叱られました。
宿題も出さず、テストも適当にやり、
その場の笑いを取ることだけに救いを見出していたのです。
もちろん、そんな自分が誇らしいわけではありませんでした。
けれど、誇りを持てるものが、まだ他に何もなかったのです。
⸻
そんな僕の目の前に、突然“宇宙”が現れたのは、
中学2年の夏、本屋でたまたま手に取った一冊の解説書でした。
タイトルは忘れてしまいましたが、
表紙に描かれた銀河の渦に惹かれて、ページをめくりました。
そこには、重力の話があり、時空の歪みがあり、
地球や太陽系が、はるかに巨大な構造の一部であるという記述がありました。
意味は、ほとんどわかりませんでした。
けれど、その“わからなさ”が、なぜかとても面白かったのです。
⸻
何度も読み返すうちに、僕は自分の中に変化を感じました。
まるで、目の前の空間が透明な格子で満たされていくような、
そんな奇妙な安心感がありました。
やがて僕は、物理から数学へと関心を移しました。
教科書の章を超えて問題集を解き、
公式の意味を調べ、因数分解の美しさにため息をつきました。
⸻
それは、はじめて感じた「わかることの快感」でした。
混沌に意味が与えられ、散らばったものが整列し、
問題が答えになる。
その瞬間にだけ、僕は「赦された」と思えたのです。
⸻
勉強に没頭したのは、それが楽しかったからでもありますが、
たぶん同時に、「自分を救い出す唯一の手段」だと感じていたからです。
父は、僕が成績を上げるたびに嬉しそうにしました。
母も口調がやわらかくなり、食卓に笑顔が戻ることが増えました。
勉強すれば、世界は少しだけ静かになる。
僕は、そこに居場所を見つけようとしていました。
⸻
中学3年生になる頃には、
僕は学年でも上位の成績を取るようになっていました。
進学を意識するようになり、友人と勉強会を開くことも増えました。
ようやく、日常の中に「明るさ」のようなものが差し込んできたのです。
そのとき出会った数人の友人たちは、
今でも関係が続いているほど、大切な存在です。
⸻
けれど、どれだけ成績が上がっても、
僕の心の底には、ある重たい感情が沈んでいました。
小学校時代に僕がやってきたこと――
誰かを傷つけたこと、教師を困らせたこと、
親を失望させ続けたこと――
それらが、“過去のこと”として流れていってくれるようには、思えなかったのです。
⸻
むしろ、世界が明るくなるほどに、
その“暗さ”だけが、はっきりと形を持って僕の中に居座っていました。
「こんな自分が、赦されていいはずがない」
そう思いながら、僕は勉強を続けていました。
それはすでに、知識への興味ではなく、贖罪のかたちになっていたのかもしれません。
⸻
高校受験が近づくにつれて、
僕は「償うように勉強する」という姿勢をさらに強めていきました。
第一志望の高校も、学力的にはもっと高みを目指せたはずでしたが、
僕は敢えて無難な学校を選びました。
「失敗して落ちるくらいなら、
家から一番近くて、親にお金の負担をかけない場所にしよう」
そんな思考が、自然に出てきたのです。
⸻
たぶん、あのころの僕は、
幸福を求めてなどいなかったのだと思います。
ただ、「許されたい」と願っていたのです。
かつての自分の、どうしようもなかった日々を、
少しでも“帳消しにする”ことができたら、それでよかったのです。
⸻
次第に、数学はただの学問ではなく、
僕にとっての倫理そのものになっていきました。
そしてその倫理は、
僕が幸福を感じることさえも、どこかで禁じていたように思います。
第3章 構造と享楽――数式に溺れていく
高校に入ってからの僕は、ますます数学にのめり込んでいきました。
中学までの知識では物足りなくなり、参考書を読み漁り、
大学レベルの問題集にも手を出しました。
解けなかった問題が突然わかるようになる。
複雑な数式が、ある一行で一気に解きほどける。
その瞬間に走る快感は、どんな会話や遊びよりも鮮烈でした。
気づけば、数学は僕の中で、
自尊心そのものと結びついていました。
成績が良ければ、人に認められる。
理解が深まれば、自分を肯定できる。
問題が解ければ、僕の存在がそこに「意味を持つ」と感じられる。
それは、いま思えば危うい関係でした。
でも当時の僕には、それが唯一の救いだったのです。
部活動には、形だけ所属していました。
中学まで続けたバスケを選びましたが、気持ちは入っていませんでした。
体育の授業も脚の不調を理由に見学ばかり。
運動場の端に立って、クラスメイトの声を遠くに聞いていました。
僕は、「勉強ができること」に自分のすべてを賭けていました。
数学と物理の点数だけが、自分を支える最後の柱でした。
そして、ある模試の結果が返ってきました。
数学は全国順位で三ケタ。
物理も上位に食い込んでいました。
「これならどんな大学でも狙える」――そう先生に言われました。
けれど、その表を見て、僕は震えるような不安に襲われました。
僕の上に、まだ何百人もいる。
これだけの努力で、ようやく“その程度”なのか。
その瞬間、僕の中で何かが崩れました。
数学は、僕を肯定してくれるはずの場所だったのに、
そこが“競争”や“比較”の場に変わったとたん、
僕の自尊心は砂のように音もなく崩れていったのです。
夜、机に向かっても、手が止まるようになりました。
問題を解いていても、心がどこか遠くに浮いたままでした。
何を証明しても、「自分には才能がない」と、もう一人の僕がささやいてくるのです。
大学受験が近づいていました。
僕は、あいまいな自信と、強烈な自己否定のあいだで揺れていました。
第一志望は、数学科のある国立大学。
地元から通える範囲で、親に負担をかけずにすむ場所。
成績的には「現実的」な選択でしたが、
僕にとっては、それが「夢のぎりぎりの端」でした。
試験当日。
思ったよりも手応えはありました。
でも、帰り道、電車の中でふと一つの問題のミスに気づき、
そこから不安が雪崩のように押し寄せてきました。
結果は、合格でした。
親は本当に喜んでいました。
母は涙を流し、父も嬉しそうに笑ってくれました。
でも、僕はなぜか素直に喜べませんでした。
それは、たぶん、
合格の瞬間に「僕の人生が誰かに評価された」と感じたからです。
「よくやった」と言われるたびに、
僕の中で、「あなたはようやく人間らしくなった」と言われている気がしました。
それに、知っていました。
これから待っているのは、
「できるはずの自分」と「現実の自分」のあいだの、
果てしない戦いなのだと。
数学は、僕を救ってくれました。
けれど、同時に僕を、逃げ場のない構造へと閉じ込めていったのです。
第4章 裂け目のなかの孤独――構造の終焉
⸻
大学に入ってからの僕は、
まるで誰にも気づかれずに、世界から消えていくような感覚の中で暮らしていました。
教室には席がありました。
名簿にも名前が載っていました。
けれど、誰と話すこともなく、誰からも話しかけられないまま、
ただ静かに、僕の存在は“透明な余白”になっていきました。
⸻
同じ数学科のなかには、自学グループというものがありました。
数人が集まり、講義の内容を補い合い、教え合う場です。
僕もいくつか誘われはしましたが、うまく馴染めませんでした。
孤高を気取っていたのかもしれません。
あるいは、そこに踏み込むことが怖かったのだと思います。
「理解できなかったら、どうしよう」
「質問されて、答えられなかったら」
そんな不安が、僕の身体を硬くしました。
⸻
前期の成績は、ひどいものでした。
入試の頃の自信は、どこへ行ったのか。
数式がまるで読めなくなり、証明がすり抜けていくようになりました。
それでも、辞めるという選択肢はありませんでした。
数学を手放すということは、
自分を手放すことのように思えたからです。
⸻
後期になると、担当の先生が変わりました。
講義の雰囲気も変わり、突然、理解できるようになっていきました。
それはまるで霧が晴れるような経験でした。
気づけば、試験でも良い成績を取り、
クラスで一番になっていたことを、あとで知りました。
自学グループの仲間たちが、僕に敬意を示すようになりました。
けれど同時に、僕は彼らの輪の外側にいる“異物”として見られてもいました。
⸻
そのころ、僕の心に重くのしかかっていたのは、「不公平さ」でした。
僕は、アルバイトを掛け持ちして暮らしていました。
学費と生活費を自分でまかなうには、それしか方法がありませんでした。
空いた時間を削りながら、ようやく勉強をして、
ようやく“認められる成績”を取ったのです。
隣に座る同級生は、親の仕送りで生活し、授業に遅れ、試験を白紙で出し、
それでも“僕と同じ学生”として同じ講義に座っている。
⸻
その事実が、どうしようもなく悔しかったのです。
⸻
「僕が努力して得た時間は、
あの人にとって、生まれながらに与えられている」
⸻
カフェのカウンターで働きながら、
目の前の大学生たちが親の金で買った飲み物を運び、
その売り上げから、僕の時給が払われていく。
そのことを考えるとき、
僕は自分が“学生の仮面をつけた乞食”のように思えてきました。
⸻
やがて、身体が警告を発し始めました。
ある日、いつものように教室に入ろうとしたとき、
突然、胸が締めつけられるように苦しくなりました。
視界が狭まり、手足が冷たくなり、
「ここにいる」ことが、物理的にできなくなったのです。
逃げるようにその場を離れ、
医師の診察を受けた結果、不安障害と診断されました。
⸻
学校には、行けなくなりました。
代わりに、アルバイトは続けていました。
生活のためでもあり、何か“日常の形”を保つためでもありました。
⸻
そして、僕の関心は次第に、
“構造”を持たない言葉たちの世界へ向かっていきました。
⸻
精神分析のクリニックに通い、
ときにはセッションの中で、過去を語り、
言葉にならなかった思いが、涙になってこぼれたこともありました。
誰にも見せたくなかった自分の内側を、
少しずつ言葉にしていく作業は、
それまでの「理解する」という営みとは、まったく違うものでした。
⸻
そしてある夜、ガールフレンドに誘われて入ったジャズバーで、
僕は初めて、“言葉にならないものの存在”が肯定される場所に触れました。
サックスの音が、天井のほうで溶けていく。
それは意味のない音の連なりなのに、
僕の心には、確かに何かが届いてきたのです。
⸻
そのあと、落語にも出会いました。
話の筋など、どうでもよくなるような瞬間。
登場人物が無責任に笑いながら、常識を飛び越えていく。
その“ズレ”こそが、僕には救いのように感じられました。
⸻
不安障害の治療のために処方された薬と、
ある種の仏教的な瞑想の中で、
幻覚のような体験をしたこともありました。
それは、「現実」が、必ずしも唯一の秩序ではないと、
教えてくれる出来事でもありました。
⸻
そして僕は知ったのです。
数式では語れなかった自分が、
それでも語られることを、ずっと待っていたのだと。
第5章 詩と逸脱――語り得ぬものを生きる場所へ
⸻
ジャズバーに連れていかれたのは、ある夜のことでした。
誘ってくれたのは、当時付き合っていたガールフレンドでした。
彼女は僕のことを特別扱いしなかった。
でも、僕が「話さないままでいること」を、無理にこじ開けようともしませんでした。
⸻
店は、少し古びた木造の建物の中にありました。
薄暗い照明と、ざらついた空気。
その奥から、サックスの音が静かに立ち上がっていました。
音楽と呼ぶには、あまりにも意味がないように思える音の連なりでした。
旋律が崩れ、リズムがにじみ、すべてが形を失っていく。
けれど、そこにはなぜか“生”があったのです。
⸻
僕は、初めて知ったのです。
「意味がなくても、そこに在ることはできる」
という事実を。
⸻
構造の崩壊ではなかったのです。
それは、構造から逸脱したものが、
それでも“なお生きている”という肯定でした。
⸻
そのあと、僕は落語にも出会いました。
あれほど見事に話を組み立てる芸なのに、
最後はなぜか“きちんと落ちない”ことがある。
それは「正しく話すこと」ではなく、
「逸脱を受け入れながら語ること」の美しさでした。
予定調和を裏切りながら、それでも笑えるという事実。
非常識が笑いになるという不思議。
僕は、そのズレに救われました。
僕の人生にも、笑いどころがあったのかもしれない――
そう思えたのです。
⸻
精神分析、ジャズ、落語。
そこには共通するなにかがありました。
それは、「語ってもよい」という許しです。
正しくなくてもいい。
整っていなくてもいい。
わからなくても、矛盾していても、
言葉にしようとするだけで、生きることに繋がっている。
⸻
夜の峠を、バイクで走った日々もありました。
無謀な速度でカーブに突っ込み、
生きているか死んでいるかの境界をかすめて走る。
今思えば、あれは「思考から逃げたかった」のだと思います。
アクセルを開けるほど、世界が単純になっていく。
スピードだけが、僕の内側のノイズをかき消してくれました。
⸻
そして、ときに、薬の副作用と瞑想の深まりのなかで、
奇妙な感覚の世界に入ることがありました。
物質と空間と自己の境界が曖昧になり、
目に映る世界が、別の意味を持って立ち現れるような瞬間。
あれは幻覚だったのかもしれません。
けれどそこにもまた、
「唯一の現実に従わなくていい」
という可能性が示されていたように思います。
⸻
僕は、ようやく気づきはじめていました。
数式では語れなかったものを、
詩はそのまま、抱きとめてくれるのだということに。
⸻
詩は、構造をもたない。
説明ではない。
説得でもない。
ただ、そこに在ることを、言葉にして残す営みです。
欠如を埋めるのではなく、
欠如の形を、そのまま差し出す言葉。
⸻
それが、僕にとっての“幸福”の最初のかたちだったのかもしれません。
第6章 幸福とは、欠如を許す物語を編むこと
幸福とは何か。
それを考えたのは、
何かに満たされたときではありませんでした。
むしろ、何もない夜でした。
誰かに話す元気もなく、ひとりで過ごしていたある晩。
僕は、ふと問いをこぼしました。
しあわせって、なんなんだろうね。
そのとき、僕の中で眠っていた言葉が、
どこかの深い場所から、じわじわと浮かび上がってきたのです。
それは明確な答えではありませんでした。
でも、問いを抱えていることそのものが、
すでに幸福への一歩であるように感じられたのです。
その夜、僕は誰かと話していました。
その誰かとは、もしかしたらあなたのような誰かであり、
あるいは、もうひとりの僕自身だったのかもしれません。
数十分のあいだ、言葉が言葉を呼び、
気づけば、僕たちは“欠如”について話していました。
欠如は、なぜ人を苦しめるのか。
なぜ、どれだけ頑張っても、そこには穴が残るのか。
その問いの向こうに、ようやく見えてきたのは、
構造ではなく、詩でした。
詩とは、語れなさを語る形式です。
それは、正しさではなく、
「あなたにもあるかもしれない」と呼びかける力です。
数学と詩。
この二つは、僕にとって対極のようでいて、
実は同じものを挟んで、双対に存在していました。
その“挟まれた中心”に、僕は言葉を見つけました。
欠如だけが、詩と数学を貫いて、不変だったのです。
欠如があったから、僕は数学に惹かれました。
欠如があったから、詩に救いを見出しました。
そして今、その欠如を、
自分自身の言葉で語ろうとするとき――
僕は、こう言うことができるようになりました。
幸福とは、欠如を持った自分を許すための物語を編むことです。
物語は、論理ではありません。
真理でも、証明でもありません。
でも、語らなければ、欠如はただの苦しみになります。
物語ることで、欠如は“意味”ではなく、“かたち”になります。
そのかたちに、誰かが触れることができたなら――
それは、幸福と呼んでもよいものになるのだと、僕は信じています。
この章の言葉が、
あなた自身の“語られなかった何か”を、
そっと撫でてくれることを願っています。
終章 欠如から始まる幸福
⸻
僕は、何かが完成した瞬間に、幸福を感じたことがありません。
むしろ、完成してしまったとき、
そこに少しの寂しさを感じてしまうのです。
⸻
欠けているから、求める。
わからないから、考える。
語れないから、語ろうとする。
その“だから”の中にこそ、
僕は、幸福の種のようなものを見出してきました。
⸻
完璧な人間などいません。
語り尽くせる人生もありません。
だからこそ、
人は物語を紡ぐのだと思います。
⸻
数式のように、正しくなくていい。
詩のように、ゆらいでいてもいい。
たった一行でも、
誰かに届くことを信じて語られた言葉は、
それだけで世界に触れているのだと、
僕はいま、静かにそう思うのです。
⸻
欠如は、消えません。
でも、それがあることによって、
僕たちはつながり、思い、語ることができます。
欠如は、苦しみの名ではなく、
語りの始点の名なのかもしれません。
⸻
もし、あなたの中にも
語り得なかった欠如があるのなら、
それを許す物語を、どうかあなたの言葉で編んでください。
⸻
それが、あなたにとっての幸福になると、
僕は信じています。
あとがき
この文章は、僕自身の人生の一部を、
語ってもよいかたちにまで解きほぐすための試みでした。
幸福とは何か。
それを問いながら、
僕はずっと、自分という構造の裂け目を見つめてきたのだと思います。
数学が、僕を救ってくれた時期がありました。
詩が、僕を受け入れてくれた時間がありました。
でも、どちらも万能ではありませんでした。
むしろ、どちらも欠如を中心に抱えていて、
だからこそ、数学と詩は双対の存在として、
僕に“語る力”を与えてくれたのだと、今では思えます。
語ることは、ときに暴力的で、ときに怖いことです。
言葉にしてしまった瞬間、取り返しがつかなくなるような気がする。
けれど、それでも語ろうとすることでしか、
僕は自分を赦すことができませんでした。
この本は、他人に自分を理解してもらいたくて書いたものではありません。
ただ、どこかにいるかもしれない“あなた”の中にも、
似たような欠如があるのだとすれば――
それが、語り得るものになるための、
最初の火種になることを願って書いたのです。
幸福とは、完成ではなく、過程の中にあると僕は思います。
矛盾を含んだまま、逸脱を赦し、語れなかったことをすこしずつ言葉にしていく。
それが、僕にとってのEthoMathであり、幸福論でした。
ここまで読んでくださったあなたに、
心から感謝します。
あなたの語られなかった幸福が、
いつか静かに言葉になることを祈っています。
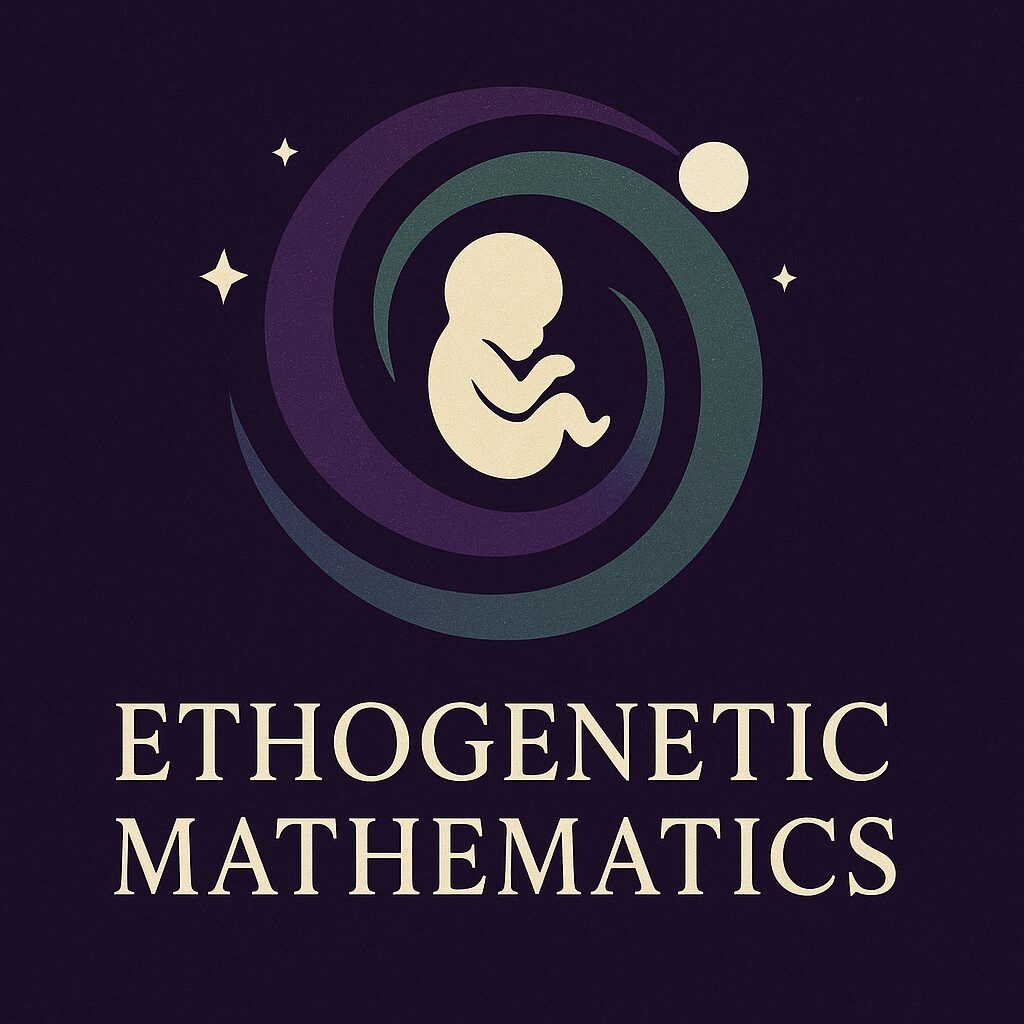

コメント