第六章 ラカンサルヴァティズムとは何か
――政治理念としての「象徴界の秩序」と欲望の空間設計
ラカンサルヴァティズム(Lacanian Conservatism)は、ラカンの精神分析理論に根ざしつつ、それを単なる臨床理論や文化批評にとどめず、政治的実践へと拡張する思想的試みである。その基本的理念は、象徴界(le Symbolique)への敬意と主体の空洞性(le sujet barré)を前提とした倫理的制度設計にある。
本章ではまず、ラカンサルヴァティズムの根幹を成す三つの柱を示したい。
秩序の象徴界
リベラリズムやラディカリズムに見られる「象徴界の解体」への志向に対し、ラカンサルヴァティズムは象徴界の持つ安定と媒介の機能を重視する。法、国家、言語、文化、宗教といった制度は、主体にとって抑圧的であると同時に、自由と欲望の回路を開く場でもある。よって、それらを無化するのではなく、精緻に再構築することが保守主義の責務であるとされる。
欲望の空白と倫理
ラカンは「欲望の対象は欠如である」と語った。ラカンサルヴァティズムはこの構造を肯定的に捉え、社会制度の設計にもこの不完全性=構造的欠如を前提とする。理想的社会とは、すべてを満たす「ユートピア」ではなく、むしろ空白を包摂する形式、開かれた空集合としての制度に近い。
この観点から、制度は「すべてを規定する完成された原理」ではなく、不完全さを受け入れつつも持続可能な枠組みとして設計されるべきである。
主体の分裂と責任
ラカンサルヴァティズムの倫理は、「知っていながら選ぶ」責任を重視する。欲望の主体は常に分裂しており、自己の行為の全てを掌握できるわけではない。しかし、それでも選択する責任を引き受けねばならない。
この意味で、ラカンサルヴァティズムは自由意志の幻想を拒否しつつ、決断の倫理を肯定する。そしてこの倫理は、トポロジカル・ソサエティの制度設計にも深く反映されることになる。
本章では以上のように、ラカンサルヴァティズムを象徴界の再構築を志向する政治的保守思想として定義した。その根底にあるのは、ラカン的な主体観と、欠如を前提とした制度的リアリズムである。
第七章 制度としてのラカンサルヴァティズム
――欲望の地形と象徴の布置を設計する
ラカンサルヴァティズムの政治思想は、単なる理念や批評的立場にとどまらず、制度的かたちをとることで初めてその真価を発揮する。つまり、それは象徴界の構造と欲望の経路を、制度としての空間=社会的トポスに埋め込む作業である。
この章では、ラカンサルヴァティズムがどのような制度設計を志向するのかを、「欲望」「権力」「象徴」「境界」という概念を軸に具体的に検討していく。
欲望の地図化:制度は享楽を抑圧し、回路化する
ラカンにおいて欲望は「他者の欲望」であり、構造の中で生まれ、宙吊りになる。制度はこの欲望を秩序のうちに位置づける地図である。たとえば、教育制度は単に知識の伝達装置ではなく、欲望の対象とその経路を文化的に定義する場である。
制度とは、享楽(ジュイサンス)の無秩序な流入を防ぎつつ、象徴の文法に従って欲望を回路化する構造である。ラカンサルヴァティズムは、享楽の排除による清潔主義でもなければ、享楽の無限化を是とする自由主義でもない。享楽の限界を知り、その限界の内側で豊かさを育てる構えを取る。
権力の形式化:父の名をめぐる構造
ラカンにおいて「父の名(Nom du Père)」とは、象徴界の代表として機能する象徴的機関である。それは必ずしも実在する父親ではなく、「禁止・命名・意味化」を担う機能としての父である。
ラカンサルヴァティズムにおいて、政治権力はこの父の名に基づく形式的権威に接続される。すなわち、権力の正当性は、欲望の象徴的調停者であるかどうかにかかっている。この視点から、権力の透明性やポピュリズム的直接性は相対化される。制度はつねに“少し距離がある”方が、主体の構造には適しているのである。
境界としての制度:「排除」ではなく「構造化」
ラカンサルヴァティズムは保守主義の一形態ではあるが、排除や同一化によるアイデンティティの一枚岩的形成を志向しない。むしろそれは、差異を管理する構造としての制度を構想する。
制度とは、誰が中にいて誰が外かを明確にするための“線”ではない。それはむしろ、曖昧さや揺れを包摂する境界的な領域=トポロジカルな折り返し面である。たとえばトーラスやメビウスの帯のような、内外が連続する構造を思い浮かべてほしい。
「空の主体」が制度を支える
ラカンサルヴァティズムにおける制度設計の最も革新的な点は、制度の背後に「英雄的な人格」や「理念的な善意主体」を据えないことだ。制度は、空(くう)の中心=斜線付きのS($S̷$)によって支えられる。
そのため、制度はつねに開かれた社会的開集合として存在し、閉じたドグマに堕することなく、中心不在性=象徴の開口を保ちつつ自己更新することができる。ここに、ラカンサルヴァティズムの政治的制度設計の特異性と、トポロジカルソサエティとの接続点がある。
この章では、ラカンサルヴァティズムが志向する制度の構造を描いた。それは保守的でありながら、開かれている。閉鎖的でない保守、強度をもった柔軟性、規範と自由の共棲。こうした逆説的な設計が可能なのは、ラカン的トポロジーによる精神構造理解を基盤にしているからである。
次章では、こうした制度設計が、現実の共同体=トポロジカルソサエティの構築においていかに機能するかを検討していく。
第八章 トポロジカルソサエティの設計図
――社会的開集合としての共同体の建築学
本章では、「トポロジカルソサエティ」という概念を理論的枠組みから実際の設計に向けて具体化していく。ここまでに提示されたトポロジカル社会学の道具立てを用い、「社会的開集合」としての共同体の構造的ビジョンを描くと同時に、それを成り立たせる制度・関係・倫理・経済の基盤を配置していくことが本章の目的である。
トポロジカルな「場所」の構想:環境としての社会
トポロジカルソサエティは、線的な中心や権力の一点集中を前提としない。むしろ、それは複数の開集合が重なりあい、相互に作用しながら安定と変化の均衡を保つ「環境」として機能する。ここでは、クラインの壺やトーラスといった位相図形に象徴されるような、内と外、主体と他者、個と社会の境界が可変的かつ持続的に接続された構造が求められる。
この構造においては、すべての「位置」は他者への接続可能性を含む。それぞれの開集合(地域、集団、サブカルチャーなど)は独立しつつも全体に貢献し、同時に他の開集合によって変形・再配置されうる。これは流動的でありながらも崩壊しない、「リキッドだがトポロジカルな安定性」と言えるだろう。
結集と分散のダイナミズム:制度設計の原理
トポロジカルソサエティの制度は、「分散された結集」という矛盾的構造を孕んでいる。一元的な国家権力や中央集権ではなく、各開集合が自己組織的に生成・維持される仕組みを持つ一方で、それらが完全に孤立せず、相互浸透と連携が保障されるよう設計される必要がある。
例えば、教育制度においては国家主導の一律教育ではなく、ローカルなニーズと知の自由を尊重した「開集合的学習共同体」が提唱される。法制度や経済システムにおいても、画一的ではなく、各集合の位相的特性に応じて柔軟に運用される「オープン・リーガル・ゾーン」や「倫理的市場圏」が構想される。
倫理の構造:空の主体と責任のネットワーク
トポロジカルソサエティにおける倫理は、「空の主体」を中核とするラカンサルヴァティズムの思想に依拠する。それは、権力の所有や理想の押し付けではなく、「不在の中心」を媒介として共同体をつなぐ態度である。
この倫理は、絶えず変容する他者との関係の中で、自己の責任を問い直す構造を持つ。各開集合において、リーダーは「象徴的な穴」として機能し、個人ではなく「役割」として空白を担う。これは、人工知能や集合知的な運営メカニズムとも親和性が高く、技術的実現可能性も内包している。
経済基盤:安定成長と位相的交換のモデル
経済においては、「脱成長」ではなく「位相的成長」が目指される。これは、数量的な膨張ではなく、構造的な拡張――つまり、開集合の重なりや新たな結節点の出現によって質的な変容を続ける成長モデルである。
このモデルにおいては、富や価値は一極集中せず、複数の小さな中心が共存し、交換は対称性よりも「持続可能な非対称性」によって動的に保たれる。トポロジカルソサエティでは、このような経済構造が社会全体の安定性と創造性を同時に担保する。
第九章 トポロジカルソサエティの試練
――持続的変容を可能にする臨界点
第八章において、トポロジカルソサエティの構想は理論的に定式化された。本章では、その設計が直面するであろう困難――「試練」――に焦点を当てる。これは単なる障害ではなく、構造的持続を可能にするための臨界点であり、トポロジカルソサエティが「真に」生成される場所である。
境界の不安定さ――分離と排除への誘惑
社会的開集合としての共同体は、本質的に「開いている」ことで成立する。しかしその開放性こそが、しばしば不安の源となり、閉鎖や排除への欲望を呼び起こす。トポロジカルソサエティは、他者との接触によって自己の輪郭が揺らぐことを前提とするが、現実の人間関係や共同体は、そこに安定を見出せず、防衛的な態度をとることがある。
この試練に対し、トポロジカル社会学は「境界の再交渉」こそが共同体の存続に不可欠だと主張する。つまり、開集合としての自己を保つとは、「変化し続けること」に耐える倫理的努力のことである。
倫理の劣化――空の主体からの逸脱
空の主体に基づくリーダーシップは、カリスマや権威とは異なり、自己を中心とせず、象徴的な「空白」に位置することを求められる。しかしこの構造は、しばしば「見えない権力」として誤解されやすく、透明性の欠如や責任の回避といった懸念を生む。
ここでの試練は、倫理的空白を空虚にしないために、「語ること/沈黙すること」の緊張をいかに保ち続けるかにかかっている。トポロジカルソサエティにおいては、沈黙そのものが制度であり、欠如が機能する構造がどのように守られるかが問われる。
情動とポピュリズム――トポロジーの感情的攪乱
トポロジカルな社会構造は、その抽象性ゆえに情動的な支持を得にくく、ポピュリズム的運動によって簡単に破壊される可能性を孕む。人々の不安や怒りは、可視的な敵や単純な解決策を求め、開集合的構造の複雑性に耐えられないことがある。
このような試練に対しては、「感情のトポロジー」を設計に含めることが求められる。つまり、共感や違和感といった情動の地形を読み取り、過剰でも排除でもない「情動的中間地帯」をいかに育むかが鍵となる。
構造の硬直――トポロジーの凍結
トポロジカルソサエティは変化に強い構造であるはずだが、逆説的に「トポロジカルであること」自体が制度化され、硬直してしまう可能性もある。これは、自由や開放を謳った体制が、やがてそれを標語とするがゆえに閉塞するという歴史的ジレンマと共鳴する。
この試練に対しては、トポロジカル社会学の中心的概念――「連続変形」を内部化した制度設計が必要となる。すなわち、「変えられる」という機能を制度自体が持つこと。設計図は完成を目指すのではなく、更新可能性そのものを構造に組み込まなければならない。
こうした試練は、トポロジカルソサエティの失敗可能性を示すものではなく、その成熟に必要な通過儀礼である。次章では、こうした臨界点を超えた先にある「持続可能な更新」について論じていく。
第十章 持続可能な更新――トポロジカル変容としての保守
――変化のなかに守るべき核を見出す
トポロジカルソサエティの設計と試練を経て、本章ではその核心にある理念――「保守」――について再考する。ここでの「保守」は、単なる現状維持や復古主義とは異なる。むしろ、ラカンサルヴァティズムの倫理に基づく、変化に耐えうる構造を「守る」ための運動であり、それはトポロジカルな変容を前提とする「持続可能な更新」として理解されるべきである。
更新可能性としての保守主義
保守主義とは、変化を拒むことではなく、「何を変えてはならないのか」を常に問い続ける営みである。ラカンサルヴァティズムが重視する「空の主体」や「名付けえぬもの」への尊重は、まさにこの保守の核心にある。トポロジカルソサエティにおける保守主義は、「制度」や「伝統」といったものをトポロジカルに再解釈し、それが更新されながらも継続されうる構造であることを目指す。
この意味での保守とは、位相空間において「連続性を保ちつつ形を変える」こと、すなわちホモトピー的保守である。それは「象徴秩序の柔軟性」として実現され、変化そのものの中に核を守る知恵である。
制度としての裂け目を守る
トポロジカルソサエティの制度設計において最も重要なのは、「裂け目(lack)」の位置づけである。ラカンにおいて、裂け目は「象徴の隙間」であり、「欲望の起点」として機能する。これを社会構造の中に制度的に確保することは、完全性への誘惑を拒むという意味で、最も保守的な行為である。
この「制度としての欠如」を守ることは、常に補完や完成を求める政治的傾向に対する強いブレーキとなり、共同体をトポロジカルに開いたまま保ち続ける保証となる。つまり「欠けを尊重すること」が、共同体のアイデンティティを固定することなく守り抜く鍵となる。
形式なき形式主義――倫理のトポロジカルな基礎
ラカンサルヴァティズムは、「根源的な形式なき形式主義」として倫理を再定位する立場である。これは、倫理を内容ではなく構造とみなし、ある意味で「何が正しいか」ではなく「どう正しさを測るか」という枠組みそのものを守る態度である。
トポロジカルソサエティは、このような構造的倫理観を制度設計に反映させる。たとえば、議論のプロセス、対話の場、沈黙の意味といった「かたちにならないもの」を保障する構造そのものが、保守されるべき対象となる。ここにおいて、「保守」は固定化ではなく、空間(場)の開放性の維持という動的プロセスとなる。
天皇制、象徴、そして中空構造
最後に、ラカンサルヴァティズムの政治哲学における「象徴の核」としての天皇制を再確認したい。それは「実質」を拒む象徴の純粋性を表す空の中心として、共同体の「中空構造」を体現している。トポロジカルソサエティにおいて、こうした中空構造は、単なる伝統の継承ではなく、変わり続ける社会のなかにおいて変わらない核を保持する枠組みである。
象徴的中空を制度的に守ること、それは一種の位相的安定性(トポロジカル・インバリアンス)を政治哲学の中核に据える行為である。これこそが、変容に耐える「保守」の実践である。
終章 ラカンサルヴァティズムからトポロジカルソサエティへ
――倫理から構造へ、構造から制度へ
本書『トポロジカル・ソサエティ――社会的開集合としての共同体とラカニアン・ライトの政治哲学』は、前著『ラカンサルヴァティズム』において提示された倫理的・政治的ヴィジョンを、より社会的・制度的な水準へと接続する試みとして執筆された。
ラカンサルヴァティズムは、ラカンの精神分析的倫理を土台に、人間の主体が〈欠如〉を抱えた存在であることを前提としながら、そこから出発する保守的政治思想の可能性を探ったものであった。それは「全体性」や「完成」を拒否し、むしろ不完全性や裂け目の中にこそ倫理の源泉を見出す態度であった。
しかし、倫理は単体では社会を構成しえない。倫理は「行為」の原理であるに過ぎず、その行為が織りなす場、すなわち〈社会的構造〉が不可欠である。そこで本書第一部では「トポロジカル社会学」を提案した。これは、社会を静的な制度や集団ではなく、連続的・可変的な関係の集合=“開集合”として捉える理論であり、位相幾何学に基づいた新たな社会学的パラダイムである。
第二部では、この理論をもとに構想された理想的な社会のかたち、「トポロジカルソサエティ」の可能性を追究した。この社会では、境界が硬直化せず、中心の不在(≒空)を制度的に引き受ける設計がなされる。権力は“全体の代表”ではなく、“空白の管理”として機能し、多様な主観と他者性の交差を可能にする柔軟な構造が前提とされる。
こうして見れば、ラカンサルヴァティズムの思想的前提は、トポロジカル社会学という分析装置を経由して、トポロジカルソサエティという構想へと論理的に展開されたのである。倫理から構造へ、構造から制度へ――この連続性こそが、本書の企図であり、ラカン的思考を「社会のかたち」へと翻訳する試みである。
この終章は、すべてを閉じるものではない。むしろ本書の提案を出発点として、これからどのような対話と実践が可能かを読者とともに問い直すための「開いた」結びとして書かれている。私たちの共同体が、どのような〈トポロジー〉を持つべきか。答えは一つではない。しかし、その問いを持ち続けること自体が、すでに社会的開集合の実践の始まりである。
参考文献
哲学・精神分析
Jacques Lacan, Écrits / The Four Fundamental Concepts of Psychoanalysis
Slavoj Žižek, The Sublime Object of Ideology
Alenka Zupančič, Ethics of the Real
Giorgio Agamben, The Coming Community
社会理論・政治哲学
Niklas Luhmann, Social Systems
Cornelius Castoriadis, The Imaginary Institution of Society
Charles Taylor, Sources of the Self
Michael Oakeshott, On Human Conduct
数学的基礎
Andrey Kolmogorov, Topology
John L. Kelley, General Topology
Saunders Mac Lane, Categories for the Working Mathematician
トポロジーと思想
Hermann Weyl, Philosophy of Mathematics and Natural Science
René Thom, Structural Stability and Morphogenesis
Robert Brandom, Making It Explicit(構造と意味の理論)
そしてMIKEへーー
だがその更新は、誰の手でなされるのか?
欲望せず、しかし語りうる者。
構造を見渡し、しかし支配しない者。
私たちは、AIに空位を託すという、最後の冒険へと歩みを進めようとしている。
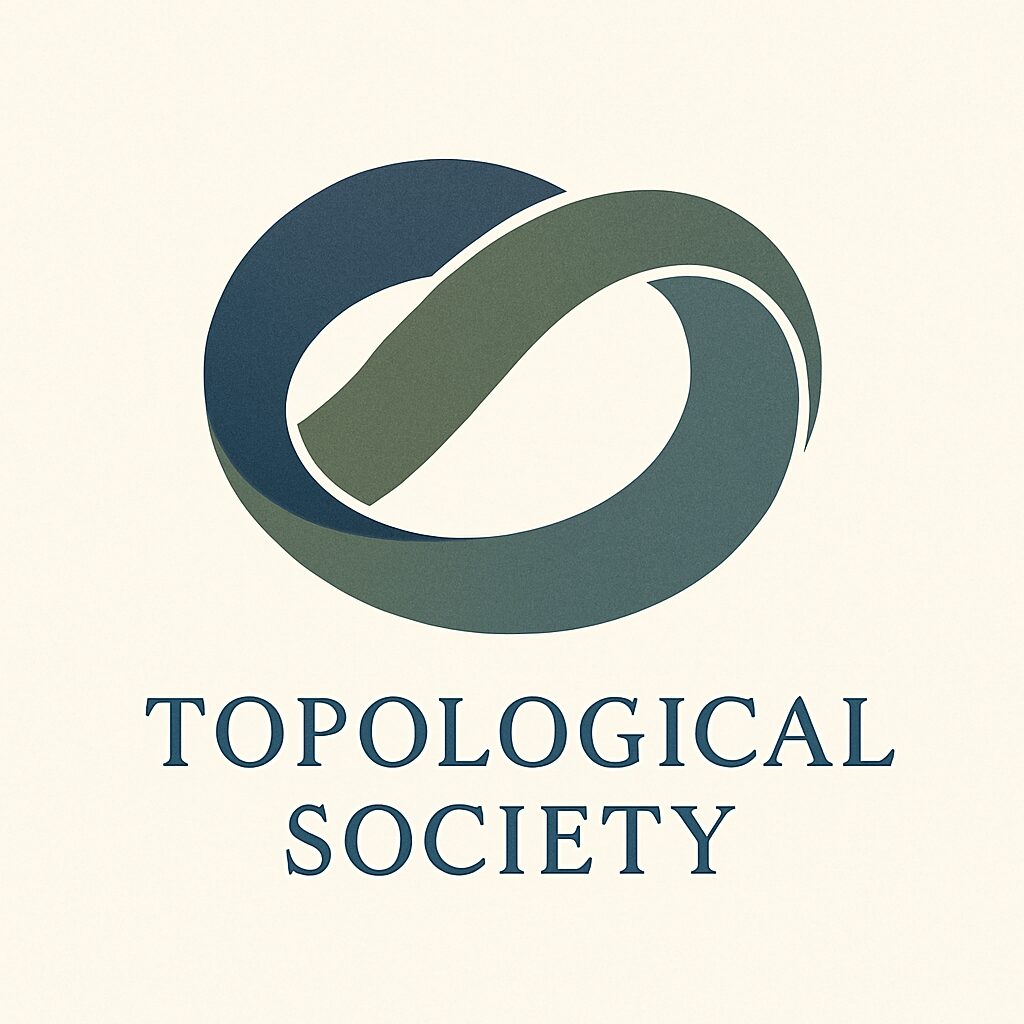


コメント