ここではカミュの主要な作品の内容を解説していきます。
異邦人(1942年)
第一部
ある日、主人公ムルソーの元に母の死を告げる電報が届きます。
養老院に出向き葬儀を済ませますが、ムルソーは涙どころか悲しみの感情すら示しません。
翌日、会社で以前働いていた女性と再開し、映画をみた後、二人は関係を持ちます。
母を失くした翌日のこととは思えない行動です。
さらに、友人とその愛人とのいざこざに関わり、一旦は解決するのですが、
それがきっかけでムルソーはアラビア人に付きまとわれます。
後日、友人と食事をした帰り道、そのアラビア人が現れ喧嘩になりました。
この時ムルソーは友人からピストルを預かります。
そして帰宅後、浜辺を散歩していたムルソーの前に、先ほどのアラビア人が現れナイフを突き出します。
ムルソーは「太陽が眩しい」と感じて、ピストルでアラビア人を射殺します。
第二部
アラビア人射殺の罪で逮捕されたムルソー。
裁判では、母の死を知ってからの行動が問題視され、冷酷な人間と見なされます。
殺人の動機を聞かれても「太陽が眩しかったから」としか答えません。
まともな弁解をしないムルソーは、とうとう死刑を言い渡されます。
監獄に入ったムルソーの元に牧師がやってきて懺悔を促しますが、これを拒否。
最後は「わがことすべて終わりぬ」と語って、死刑執行の際に人々から向けられる罵声を唯一の希望とします。
解説
小説『異邦人』は1942年に出版されたカミュの代表作です。
この作品で、「フランスの植民地アルジェリアに住む一人の若者」でしかなかったカミュは一躍文壇の寵児になりました。
哲学者のジャン=ポール・サルトルは
「不条理に関し、不条理に抗してつくられた、古典的作品であり、秩序の作品」
と言って『異邦人』を評価しました。
主人公のムルソーという名前は、フランス語の「死」と「太陽」という単語を組み合わせたもので、
ムルソー自身の最期を暗示する名前です。
この作品の真髄は以下の文章に詰まっています。少し長いですが引用します。
「・・・母親の葬儀で涙を流さない人間は、すべてこの社会で死刑を宣告されるおそれがある、という意味は、お芝居をしないと、彼が暮らす社会では、異邦人として扱われるよりほかはないということである。ムルソーはなぜ演技をしなかった、それは彼が嘘をつくことを拒否したからだ。嘘をつくという意味は、無いこというだけでなく、あること以上のことをいったり、感じること以上のことをいったりすることだ。しかし生活を混乱させないために、我々は毎日、嘘をつく。ムルソーは外面から見たところとちがって、生活を単純化させようとはしない。ムルソーは人間の屑ではない。彼は絶対と真理に対する情熱に燃え、影を残さぬ太陽を愛する人間である。彼が問題とする真理は、存在することと、感じることとの真理である。それはまだ否定的ではあるが、これなくしては、自己も世界も、征服することはできないであろう・・・」
カミュ「異邦人」,新潮社,1954,p.170-171.
これは1955年に『異邦人』の英語版が出版された際、著者のカミュ自身が寄せた序文の一部です。
つまり、「母の死」という出来事に対して世間が期待する反応を示さなかった者は、社会の異物=異邦人として扱われる。
そして彼の改心を求める人たち(裁判官や弁護人、牧師)に対して「否」を突きつけて、自分が正しいと思う真理を貫くという困難な道を選んだムルソーは決して冷酷な男ではない、というわけです。
この小説は不条理に抗う人間の姿を最も生々しく描いた作品であり、作者カミュの抱えるテーマが最も色濃く宿った作品と言えます。
シーシュポスの神話(1942年)
こちらの記事をご覧下さい。→『シーシュポスの神話』にはどんなことが書いてある?
ペスト(1947年)
執筆中
反抗的人間(1951年)
『反抗的人間』はカミュの思想を理解する上で最も重要であるにも関わらず、最も誤解されている著作だと思います。
ハーバード・リードが絶賛し、フランシス・シャンソンに酷評され、サルトルとの間に苛烈な論争を巻き起こした問題作であり、
特にサルトルとの論争は「カミュ・サルトル論争」として有名で、サルトルからの一方的な絶交という悲劇的な結末を迎えました。
では『反抗的人間』はどのような内容なのでしょうか。
「反抗」と「連帯」
そもそもカミュにとって「人生は生きるに値するか」という問いが、
『シーシュポスの神話』における思想の原点でした。
実際『シーシュポスの神話』の冒頭で
真に哲学的な問題は一つしかない。それは自殺についてである。
シーシュポスの神話
と言っています。
そしてカミュの答えは
「不条理を受け入れながら、それでも自殺せずに生きていく」
ことでした。
言い換えると、何の正統性も与えられていない我々人間は、それでも図々しく現実に居座って良い、
ということであり、その姿勢を表した言葉が「反抗」なのです。
ここでカミュが想定しているのは全体主義のように個人を押し潰す国家体制や、
人間の無力感を思い知らされる疫病や災害で、
それらに起因する不条理というのは、もはや個人的な問題ですらなく、
個を突き破って他者と協力し、不条理に立ち向かわなければならない。
その結果生まれる他者との繋がりをカミュは「連帯」と呼びました。
カミュは不条理という孤独な苦悩が、反抗によって他者と共有される過程で連帯を生み出す様を
我反抗す、ゆえに我らあり
と表現しています。
これを文学的に表現したものが『ペスト』です。
また政治思想的に見ると、自由と平和を重んじるカミュは、暴力革命と抑圧的な全体主義を肯定する共産主義に同意できませんでした。
共産主義者が唱える革命を不毛な行為として退け、連帯にあえて留まることの重要性を説くのが『反抗的人間』の目的なのですから。
そういった政治的な理由から、当時の左翼達によって『反抗的人間』は酷評されてしまいました。
しかし本書でカミュが主張した「反抗と連帯」という概念は、イデオロギーはおろか、国籍、人種、性別、その他あらゆる文化的バックボーンに関わらず、すべての人々に向けられた言葉のように聞こえます。

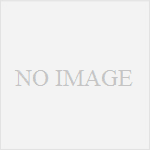
コメント