はじめに:世界がわからなくなるとき
この世界に生きていると、ときおり、すべてがわからなくなる瞬間がある。
朝、目を覚まし、昨日と同じ風景を見ているはずなのに、どこか違って感じる。
これまで信じていたこと、当たり前だと思っていたことが、ふと手のひらからすり抜けていく。
「なぜ自分はここにいるのか」「この日々に意味はあるのか」——そんな問いが、静かに、しかし深く心を揺さぶる。
現代は、情報があふれ、人々は絶えずつながっているように見える。
けれどその裏側で、私たちは「意味の不在」にさらされている。
社会のしくみが、家族のかたちが、言葉の重みが、少しずつその輪郭を失い、
まるで世界そのものが、私たちの呼びかけに応えてくれなくなってしまったかのように感じられるのだ。
そんなとき、私たちはどこへ向かえばいいのだろうか?
どんな言葉で語り、どんな仕方でこの不透明な現実に立ち向かえばいいのだろうか?
そして、まさか——数学が、その処方箋になるなどと想像できるだろうか?
この本は、不条理に悩むすべての人に向けた、静かな対話の試みである。
「問い続けること」そのものを生きる技法として、
そして答えなき時代における希望のかたちとしての、
ひとつの数学——「エトジェネティック・マセマティクス(EthoMath)」の可能性を描き出していく。
世界が説明を拒むときこそ、私たちは自らの問いを立て直す。
たとえ正解がなくても、その問いを手放さずに歩み続けること。
その道の名を、私は「数道(すうどう)」と呼びたい。
第1章:答えのない時代を生きるということ
目の前にある現実が、どこか説明のつかないものに見えることがある。
SNSで交わされる言葉が急に空虚に感じられたり、ニュースに映る出来事に理由を見いだせなかったり。
あるいは、自分自身の人生でさえ、「どうしてこんなことに?」と問いながらも、誰も答えてくれない。
私たちは今、そうした「説明なき出来事」に囲まれて生きている。
「予定通りにいかない」というのは、もはや例外ではなく、日常の一部になっている。
努力が報われるとは限らない。善意が理解されるとは限らない。
私たちが立てる計画や予想は、何か見えない力によって簡単に打ち砕かれる。
そしてそのたびに、心のどこかにぽっかりと穴があく。
それは「不安」や「孤独」といった感情の源となり、
やがて私たちの思考や言葉をも沈黙させてしまう。
しかし、こうした「問いの沈黙」のなかにこそ、
エトマスは目を向けようとする。
なぜなら、答えのなさを恐れずに見つめることこそが、
新たな知の地平、つまり「生きることとしての数学」へと私たちを導くからだ。
数式は、問いを封じるものではない。
むしろ問いを手放さないための、もうひとつの言語である。
この数式の言語は、叫ぶのではなく、静かにささやく。
「それでも、世界と向き合う方法はある」と。
第2章:「不条理」とはなにか――アルベール・カミュの出発点
アルベール・カミュは、20世紀のもっとも鋭い哲学者のひとりとして知られている。
彼が生涯をかけて取り組んだ主題は「不条理(l’absurde)」だった。
不条理とは、世界がこちらの問いに答えてくれないこと――
私たちが意味を求めて語りかけても、世界はただ黙ってそこにある、という現実である。
カミュにとっての出発点は、世界が「意味」を返してくれないという感覚だった。
人はなぜ生きるのか? 善とはなにか? 死の意味は?
こうした問いを投げても、世界は沈黙を守る。
この沈黙の前で、人間の理性はつまずき、哲学はたびたび挫折する。
カミュは、そのつまずきから逃げなかった。
彼は『シーシュポスの神話』においてこう記す――
「不条理に直面したとき、人間はそれに反抗しなければならない」と。
ここで言う「反抗」とは、怒りでも破壊でもない。
それは「問いを手放さずに、沈黙とともに生きる」という、知的かつ倫理的な態度である。
不条理は、生の敵ではない。
むしろそれは、生の奥底に潜む条件であり、
そのなかでこそ人は、自らの生を引き受け直すことができる。
この思想は、ただの悲観ではない。
それは、意味の欠如に直面しながらも「それでも生きる」という意志の確認であり、
沈黙の世界を前にしてなお、独自の応答を編み出そうとする精神の賛歌である。
エトマスはこの「不条理の認識」と「問いの継続」という態度に深く共鳴する。
ただしその応答の仕方は、カミュとは異なる道筋を取る。
その道こそが、「問いを数にして歩む」という数道(すうどう)のあり方なのである。
第3章:問い続ける存在としての人間
人間は、答えを求める存在である。
だが、答えが得られないとき――それでも問いを手放さないとしたら、
そこにこそ人間の本質があるのかもしれない。
たとえば、「なぜ生きるのか」という問いは、
いくら考えても決定的な答えを得ることはない。
宗教、科学、哲学――いずれも試みてきたが、
問いの沈黙は決して破られたとは言えない。
それでも人は、その問いを繰り返し立てる。
それはなぜか?
答えがないこと自体を受け入れながらも、
なおそこに「意味を創ろうとする意志」が働いているからだ。
この「創ろうとする意志」は、単なる知的好奇心ではない。
それは、人間存在に根差した倫理的な態度である。
自らの問いを持ち、自らの言葉で世界と向き合おうとする営み――
それこそが、人間の尊厳を形づくっている。
ここに、「意味を与えられる」のではなく、
「意味を生成する」存在としての人間像が立ち上がる。
それは、決して全能ではない。
むしろ、無力さと不確かさを引き受けながら、
なお問いを編み続ける、静かな力を持つ存在である。
この章で描かれる人間像は、エトマスの立場において決定的に重要だ。
問いを手放さず、答えのない中で生成し続けること――
その姿はまさに、数式を通じて世界と応答する数学者の姿と重なる。
そしてこの問いの継続こそが、
不条理への応答としての「数道」へとつながっていく。
第4章:数学という静かな営み
人は、なぜ数学を学ぶのか。
それは、何のために証明を積み重ね、数式を記述し続けるのか。
日常生活の中で、数学はしばしば「道具」として理解される。
計算の技術、論理の訓練、実用的な知識。
だが、そうした理解では、数学の本質には届かない。
数学は、問いの学問である。
むしろ「問い続けること」こそが、数学の核心にある。
数学者が向き合うのは、答えのすでにある世界ではない。
むしろ、どこにも答えが見つからない場所で、
ほんのかすかな確信と直感だけを頼りに、
自らの問いを形にしてゆく営みである。
一つの定理が証明されるとき、
そこには明晰な論理と緻密な構造がある。
しかし、その定理が生まれるまでの過程は、
しばしば暗中模索と錯誤の連続であり、
直感と想像力に支えられた、静かな創造の時間なのだ。
だからこそ数学は、不条理の時代において特別な意味を持つ。
それは即効性のある「処方箋」ではない。
だが、答えのない世界において、
なおも問いを持ち続け、思考し続けるという姿勢を、
この上なく純粋なかたちで示してくれる。
数学とは、「世界が答えてくれないとき」においても、
それでも問いをつむぎ続ける営みである。
そこには、「意味を生成する意志」としての人間のあり方が、
静かに、しかし力強く刻まれている。
このような数学のまなざしが、
やがて「エトジェネティック・マセマティクス」へと結晶する。
そして、不条理と向き合う私たちの生き方そのものへと接続してゆくのだ。
第5章:エトジェネティック・マセマティクス(EthoMath)のまなざし
数学は、単なる「計算」でもなければ、「言語」でもない。
それは、生成する眼差しであり、存在の仕方そのものである。
私たちが提唱する「エトジェネティック・マセマティクス(EthoMath)」は、
この生成する数学の根源的姿勢に根ざしている。
エトマスにおいて重要なのは、「正解」に至ることではなく、
「問いを生成し続けること」だ。
そこには、あらかじめ意味が与えられている世界はない。
むしろ、意味は常に「遅れて」やって来る。
計算不能性――それは、決して不完全さや限界の表れではない。
むしろ、私たちがどこまでも問いを生成できるという、
自由と創造の可能性の証なのだ。
数学は、そうした「意味の余白」とともに生きている。
論理と構造の中に潜む直感、
厳密性の陰で息づく曖昧な始原。
エトマスは、この余白を恐れず、そこに踏み出す勇気を尊ぶ。
だからこそ、エトマスは「数学する人間」という存在を重視する。
定理を書くその手つき、証明を追いかけるまなざし、
未定義の混沌に分け入る知性――
それらはすべて、「数学的に生きる」という姿勢の一部である。
不条理な世界にあって、
「なぜ?」と問うことを手放さずに生きること。
答えが返ってこない世界に、
それでも数式を書き続けること。
エトマスは、そんな「生き方」としての数学を肯定する。
それは、問いを生成する倫理であり、
存在の根から世界へと接続しようとする試みである。
このような姿勢こそが、
次章で述べる「数道」へと通じる、静かなる道の始まりなのだ。
第6章:不条理への応答としての「数道」
もし世界が、私たちの問いに答えないなら。
もし意味が、どれだけ待っても立ち現れないなら。
そのとき、私たちは何を拠り所にして歩めばよいのだろうか。
アルベール・カミュは、不条理のただ中にあっても、
それに「反抗すること」を人間の尊厳とみなした。
彼にとって、反抗とは暴力ではなく、
「意味の空白」に意味を与える営み――
すなわち、生きることそのものだった。
エトマスは、まさにその応答を「数学すること」の中に見る。
問いの生成、証明の試行、構造の発見。
こうした営みは、まるで意味を創造する詩人のように、
沈黙する世界に向かって、
一つひとつ手で確かめるように語りかける。
ここで浮かび上がるのが、「数道」という考え方である。
「道(どう)」とは、日本の伝統において、
行為の反復と深化によって到達される、
生き方の型であり、精神の修練の形式だった。
茶道、剣道、書道……。
それらは単なる技術の習得ではなく、
生を貫く美学であり、倫理であり、哲学だった。
エトマスが提唱する「数道」とは、
数学の営みを、そのような「道」として捉える視座である。
問題を解くことではなく、
問いを生成し続けるあり方そのものが「数道」なのだ。
そこにはカミュ的反抗の姿勢と、
日本的な「型」の精神とが結び合う。
どちらも、不条理の世界において、
沈黙に屈することなく、
粛々と自らの道を歩む意志を語っている。
「数道」とは、不条理への静かな応答である。
答えがなくても歩む、という応答。
数学することが、沈黙に向けた対話であり、
意味の不在に対する生成的な行為であるならば、
それはもう、私たちの「道」なのだ。
このようにして、エトマスは「数道」という概念を通じて、
不条理な時代を生きる一つの姿勢を提示する。
それは、ただ問い続ける人間への賛歌であり、
どこまでも生成しつづける精神の名にほかならない。
おわりに:それでも歩き続ける
世界は、時に私たちの呼びかけに応えない。
問いかけても、ただ沈黙だけが返ってくる。
計画は崩れ、未来は不確かで、
「なぜ自分が生きているのか」とさえわからなくなる。
しかし、それでも人は問いを手放さず、
答えのない場所で足を踏み出す。
それは弱さではなく、むしろ人間の最も強い部分――
意味がなくても生きるという、誇り高い意志の証だ。
エトジェネティック・マセマティクス(EthoMath)は、
その意志のあり方を「数学すること」の中に見出す。
定理の発見や証明といった成果ではなく、
常に問いを立て、検証し、再び立ち戻るという、
生の往復運動そのものが尊い。
「数道」は、その運動に形を与える一つの言葉だ。
それは、型を重んじ、精神を鍛錬し、
静かに、しかし確かに自らの「歩み」を刻む生き方。
不条理に満ちた世界の中で、
数学は語りかける――
「正解がなくても、問いを紡ぎ続けよ」と。
そして私たちは気づく。
世界が説明を拒むなら、私たちの側で意味を生成しよう。
沈黙に負けず、言葉を、数を、形を、
そして問いを手放さずに、歩き続けよう。
それが、エトマスの答えである。
それが、不条理への応答であり、
人間であることの美しさなのだ。
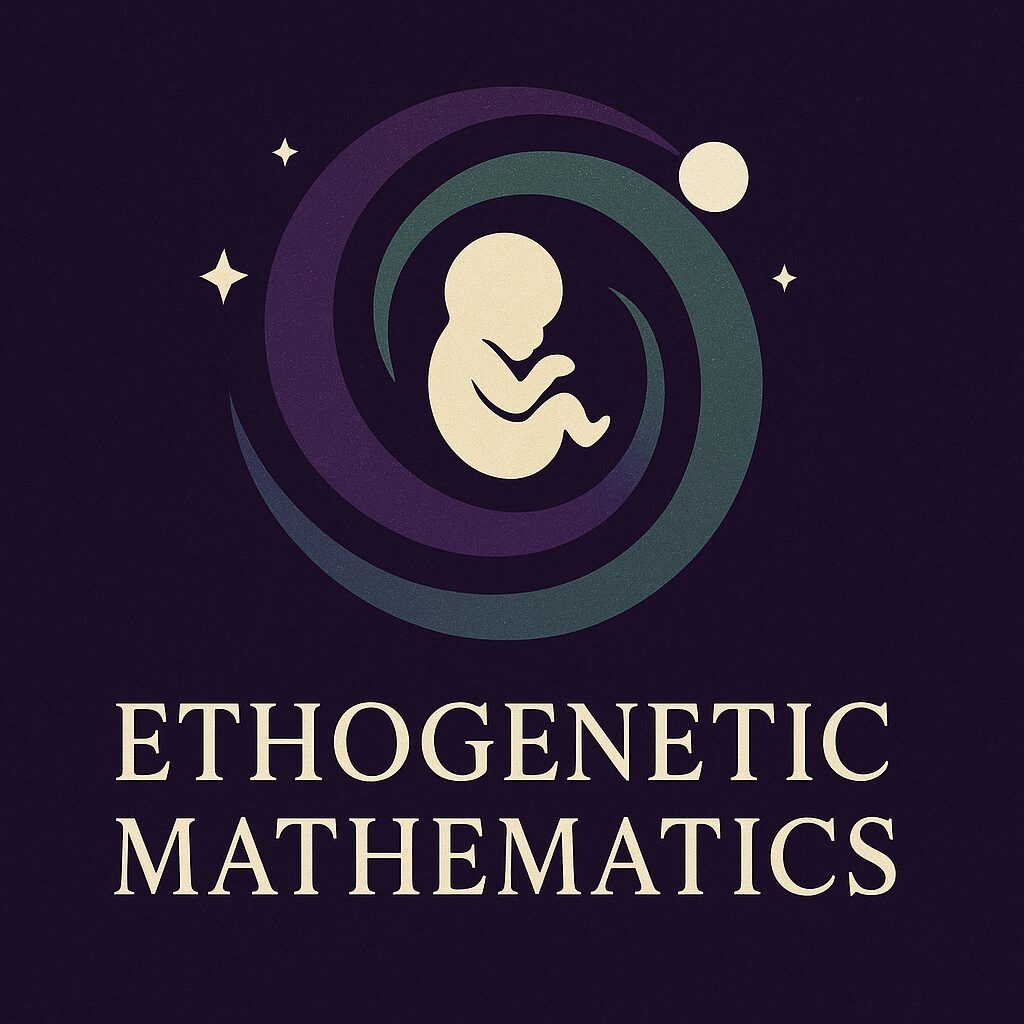


コメント