序章
ラカンサルヴァティズムから構造の政治へ
本書は、前著『ラカンサルヴァティズム』において提起された倫理的・政治的立場を出発点としながら、それをさらに深め、構造化し、制度化するための理論的試みである。前著では、ラカンの精神分析理論を足場とした保守思想の可能性が探求された。そこでは「欠如を抱えた主体」を出発点とすることで、あらゆる全体主義的幻想や、享楽への無制限な投企から距離を取る倫理が提示された。私はそれを「ラカンサルヴァティズム(ラカニアン・ライト)」と呼び、倫理のレベルで「象徴界の秩序を引き受けること」「享楽を節度あるかたちで社会化すること」の重要性を強調した。
しかし、倫理は行為を導くが、それだけでは社会は持続しない。倫理を実効性あるものとするためには、構造が必要である。そして構造とは、個々の行為を支え、可能にする〈かたち〉である。ラカンサルヴァティズムが主張した「欠如を前提とする自由」は、現実の社会制度や共同体の中に埋め込まれて初めて実現されうる。だが、現代の社会理論において、そのような構造のかたちを描き出す理論装置は、まだ十分に整備されていない。既存の社会学は制度論的に過ぎ、また過剰な流動性に傾いた社会思想は、かえって倫理的な基盤を失ってしまっている。
そこで私が提案するのが「トポロジカル社会学」である。これは、社会を「位相空間」として捉える新しい視座である。集合論的に分割された集団でもなく、流動するネットワークでもない。連続性と切断、重なりとズレ、内と外の曖昧な境界を保持しつつ構造化された空間として、社会を理解する。そのための概念が「社会的開集合」である。
「社会的開集合」とは、構成員の固定的な所属や明確な境界を持たない。むしろ、個々の主体が複数の開かれた集合に重なりながら、一つの社会的場を共に形成する構造である。それは、アイデンティティの断絶や集団の排除ではなく、接続と浸透、近傍性と可変性によって結びつけられる共同体である。
こうした構造は、単なる理論上のモデルではない。現代社会が直面する困難、たとえば政治的分断、文化的排除、情報的過飽和、アイデンティティの固定化と流動化の矛盾といった問題に、具体的に応答しうる視座を提供する。トポロジカル社会学は、こうした困難を「かたち」としてとらえることを通じて、新たな制度設計の可能性を開く。そうして生まれるのが、「トポロジカル・ソサエティ」という社会像である。
トポロジカル・ソサエティとは、社会的開集合として編まれた共同体であり、欠如を中心に据えた制度構造である。そこでは、中心的権力は空白として残され、制度は固定された命令機構ではなく、空の媒介体として機能する。これは、前著『ラカンサルヴァティズム』で提示した倫理が、そのまま社会のかたちへと翻訳されたものである。だが同時に、トポロジカル・ソサエティは、ラカンサルヴァティズムを超えて、一つの独立した社会理論として立ち上がる潜在力を備えている。
本書の第一部では、トポロジカル社会学という新しい理論装置を提示し、その基礎的な道具立てと構造の捉え方を展開する。開集合、近傍、ハウスドルフ性、結び目といった数学的トポロジーの概念が、どのように社会構造の理解に応用されうるかを追究する。そして第二部では、そうした構造がいかに制度に具体化され、政治的に実践されうるかを考察する。そこでは、トポロジカルソサエティの制度設計の可能性と、試練、そして保守としての持続的変容が議論される。
倫理から構造へ。構造から制度へ。これは、思想の重力が徐々に社会の現実に接地していくプロセスであり、本書はその中間点をなす書物である。欠如に向き合うことを恐れず、その空洞を中心に据えることで、私たちは新たな共同体のかたちを想像し、設計することができるのだ。
第1章
社会的開集合という発明―― 境界のゆらぎと接続可能性の社会学
社会を捉えるとは、何を捉えることなのだろうか。近代社会学の多くは、人間の集合、制度の構造、経済や権力の分配といった「実体」に注目してきた。しかし、現代社会の複雑性、流動性、そして過剰なアイデンティティ闘争を前にして、実体的な見取り図はもはや限界に来ている。必要なのは、「何があるか」ではなく、「どうつながっているか」を描き出す視座である。
この章で提案するのは、「社会的開集合(social open set)」という概念である。これは、数学のトポロジーにおける“開集合”の定義――「ある点を含む集合が、その点の周囲すべても含むこと」――を、社会学的に転用した概念である。つまり、社会において「誰かがいる場所」は、その人と接触可能な他者たちとの“近傍”を含むネットワーク的な構造を意味する。
この発明は、単なる比喩ではない。それは社会の在り方を、「所属」や「境界」によって定義するのではなく、「接続可能性」と「境界のゆらぎ」によって定義しようとする試みである。ここでは、国籍、性別、職業、宗教といった明示的な枠組みよりも、関係性そのものの流れと構造が重視される。言い換えれば、社会的存在は「何に属するか」ではなく、「どのように近接しているか」によって記述されるのである。
社会的開集合はまた、伝統的な「内」と「外」の二分法を崩す。開集合は、常に「他者」との接触面を持ち、完全に閉じた内部を構成しない。つまり、「私たち」という集合は、その定義のうちに、すでに「彼ら」との境界を含んでいる。このことは、共同体の設計において極めて重要な含意を持つ。すなわち、共同体とは同一性の共有によってではなく、境界のゆらぎを許容する空間構造として成立する、ということである。
この概念の導入は、既存の社会理論に対して二つの批判的応答を含んでいる。一つは、構造機能主義のように社会を閉じた安定的システムとして捉える視点への反論である。もう一つは、過剰にリキッドで分節不可能なものとして社会を描こうとするポストモダン的視座に対する距離である。社会的開集合という概念は、安定性と変化、接続と差異のあいだに、幾何学的な構造を与えることを目的としている。
この章では、社会的開集合を理論的に位置づけるとともに、その主要な性質――開放性、重なり、分離可能性、変形可能性――を説明し、これをどのように現代社会の分析に応用できるかを考察する。また、境界概念の再定義、近傍性の再考、そして「閉じられた社会」と「開かれた社会」の違いを、トポロジー的に明確にしていく。
このようにして私たちは、「社会のかたち」を再び考える準備を整える。そしてそれは、かたちが定まらない社会において、むしろ“かたちそのもの”を問い直す倫理と知の営みでもある。
第2章 トポロジーの思考とその社会学的転用
―― 開集合・近傍・ハウスドルフ性の再解釈
トポロジー(位相幾何学)は、対象の“かたち”が「連続的な変形に耐える限りで同一である」と見なす数学の一分野である。長さや角度といった量的属性ではなく、「つながり方」や「穴の有無」などの構造的属性に着目するこの視座は、物理学や生物学だけでなく、言語や認知、そして社会構造の理解にまで応用されうる抽象性と柔軟性を持っている。
本章では、トポロジーの基本概念――開集合、近傍、ハウスドルフ性――を社会理論の文脈において再解釈し、「社会的構造をトポロジカルに思考するとはどういうことか」を探っていく。
開集合と近傍――つながり方を記述する
トポロジーの中核をなすのが「開集合」である。開集合とは、ある点を含み、その点の“近く”もすべて含む集合である。言い換えれば、ある点に位置する存在が、その周囲との関係性をもって定義されているということだ。
この概念を社会に応用すると、個人や集団を「孤立した点」ではなく、「近接する関係のなかにある点」として理解することが可能になる。個人は属性によって定義されるのではなく、他者との距離感・接触可能性――つまり「近傍」によって定義される。このとき、「社会的開集合」とは、誰かの近傍が流動的に変化しうる、開かれた関係空間である。
ハウスドルフ性――分離と認識の条件
トポロジーには、「ハウスドルフ性(Hausdorff)」と呼ばれる重要な性質がある。これは、「異なる2点は、それぞれを含み、かつ互いに重ならない開集合で分離できる」という条件である。
この性質を社会に当てはめるなら、「他者を他者として尊重できる関係性の条件」として読むことができる。個人が個人として分離され、それでもなお社会的関係の中で相互に位置づけられる――これはまさに、リベラルな公共空間や個人主義的倫理が希求する理想に近い。
ハウスドルフ的社会空間とは、「孤立でも融合でもなく、分離可能性と関係可能性が共存する空間」である。
同相性と変容――「変わらないこと」の中にある変化
トポロジーでは、形を連続的に変形しても“同じ構造”と見なせることを「同相(homeomorphism)」と呼ぶ。たとえば、コーヒーカップとドーナツは、穴が一つであるという点で“同じ”トポロジーを持つ。
この発想を社会に転用すれば、「制度や価値観が表面的には変化しても、深層構造が維持されている限り同じ共同体であり続ける」という見方が可能になる。逆にいえば、「本質的構造の変容」は、制度や文化の見かけの変化よりも深く、重大な断絶を意味することになる。トポロジカル社会学は、この“かたちの保存”と“構造の崩壊”を区別する理論装置を提供する。
社会構造を〈かたち〉として捉える
従来の社会学が、制度や集団を「中身」や「機能」から捉えようとしてきたのに対し、トポロジカル社会学は社会の「かたち」に着目する。
それは、どこに裂け目があるか、どのように繋がっているか、どのように変形可能か――といった空間的・構造的視点であり、社会を「距離」「近傍」「境界」「重なり」によって記述するための理論である。
このような視座は、現代社会の複雑な移動、複数の所属、アイデンティティの重なり、多様性と分断の共存といった現象を、数量ではなく構造として捉えることを可能にする。
本章で示したように、トポロジーの考え方は、社会の捉え方を根本から書き換える可能性を持っている。それは数学の言語の借用にとどまらず、人間と社会の関係を、「配置」や「変形」の観点から再設計するラディカルな方法論である。
次章では、こうした視座の先に見えてくる社会のモデル――トポロジカル・ソサエティの全体像に迫っていく。
第3章 トポロジカル・ソサエティとは何か
―― 可変性・重なり・空白を前提とした共同体像
前章までに、トポロジーという数学的視座を社会構造の思考に応用するための基礎的な道具立てを準備してきた。本章では、いよいよその視座から導き出される社会のモデル――すなわち「トポロジカル・ソサエティ(topological society)」とはどのような共同体なのかを、思想的かつ制度的に具体化していく。
トポロジカル・ソサエティとは、一言でいえば「社会的開集合によって構成された共同体」である。そこでは、固定された境界や排他的な所属が解体され、個人や集団は「重なり合い」「ずれ」「変形」を許容しながら社会的空間を共有している。トポロジカル・ソサエティは、静的な「国」でも「民族」でもなく、連続的に変形しながら保たれる構造である。つまり、それは形を持ちながら、決して固まらない共同体なのだ。
社会的開集合としての共同体
トポロジカル・ソサエティの基本単位は、閉じた枠組みではなく「開集合」である。ある人が属している社会単位は、その人と近接する他者との関係を含み、絶えず変動する。たとえば、ある地域コミュニティは、地理的な境界よりも、そこに流れる交流・信頼・習慣といった「近傍性」によって定義される。開集合は、誰を「内側」に含み、誰を「外側」に置くかを固定せず、曖昧なままに接続されることで機能する。
このような社会構造は、流動性をただ称揚するものではない。むしろ、「緩やかに分離され、同時に重なり合う」構造を持つことで、極端な孤立や同一化を回避し、緊張を持続可能なかたちで繋ぎ止めることができる。社会的開集合という単位は、差異を排除するのではなく、差異を前提に成立する秩序である。
重なりと中空構造
トポロジカル・ソサエティにおける共同体は、しばしば複数の開集合の「重なり」によって成り立つ。たとえば、ある人は同時に、家族、職場、地域、趣味、宗教、政治団体といった複数の集合に属している。そのどれもが排他的ではなく、可変的に重なり合い、時にずれながら、全体として一つの「私という空間」を構成している。
ここで重要なのは、「中心不在」という構造である。すなわち、すべてを統合する絶対的原理や権威は存在せず、むしろ各開集合のズレや境界の曖昧さによって構造が保たれている。この「中空構造」こそ、ラカンサルヴァティズムの倫理と接続する点であり、空白を中心とした共同体の設計という、新たな社会像を可能にする。
境界=媒介としての制度
このような社会では、制度の役割も再定義される。制度とは、かつては「区切るもの」、つまり「内と外を分ける線」として理解されてきた。だがトポロジカル・ソサエティにおいて、制度は「媒介の場」である。境界は固定された壁ではなく、接触と摩擦を生むインターフェースとして機能する。
たとえば、国籍や法的所属といった制度も、もはや「唯一の所属先」として個人を囲い込むのではなく、複数の制度的近傍に部分的に接続される「多重所属の場」となる。これは「国民」であると同時に「市民」でもあり、あるいは「非所属」や「一時的所属」として制度に参与するあり方を含む。
欠如を含む持続的変形としての社会
トポロジカル・ソサエティは、常に「変形可能」である。その変形は、構造の崩壊を意味しない。むしろ、同相性が保たれている限りで、社会はさまざまな圧力や変化を受けながらも連続的に持続することができる。
ここでの「持続」とは、何も変えないことではなく、変わり続けることを引き受けながら、変わらないものを保ち続けることを意味する。そしてその保たれるべき核とは、完成された理想ではなく、「空白」や「裂け目」――つまり制度や秩序の不在の場所である。
この章で描いたトポロジカル・ソサエティは、ラカンサルヴァティズムの倫理的前提と、トポロジカル社会学の構造的視座が出会う場に生まれる新たな共同体モデルである。次章では、こうした共同体がどのように日常的な実践のなかで生まれ、維持され、変形されていくのかを、エスノメソドロジーと「結び目」の概念を通じて考察する。
第4章 結び目の社会理論
―― 社会的生成と絡まりのトポロジー
トポロジカル・ソサエティは、滑らかで均質な空間ではない。それは常に、断裂、ねじれ、逸脱、介入といった不規則性のうちに現れる。そして、そうした不規則性こそが、社会の実際の生成点である。本章では、日常的な相互行為や集団の構造の中に現れる「絡まり」――すなわち結び目(knot)のトポロジーを、社会理論として明示化する。
社会的結び目とは何か
「結び目」とは、本来は一本の紐や線が複数回絡まりあい、自分自身と重なりながら一定の構造を形成している状態を指す。これを社会的状況に置き換えれば、個人・集団・制度・言語・感情などが互いに干渉し、単線的にはほどけない複雑な構造を生み出す場面に等しい。
たとえば、ある地域における行政・住民・宗教団体・メディアの間に生じる不信と連携の複雑な網――これらは「誰が主体であるか」を単純に特定できないまま、しかし確実に力を持って作用している。このような状況こそ、結び目的構造である。
ラカンの結び目と三重構造
ここで参照されるのが、ジャック・ラカンによる「ボロメオの輪」である。ラカンは主体の構造を、「想像界・象徴界・現実界」という三つの秩序の絡まりとして描いた。どれか一つが解ければ、全体は崩れるが、同時にどれか一つが強く引き締まれば、他も引き寄せられる。
社会的結び目も同様に、異なる次元――制度的ルール(象徴)、感情・関係性(想像)、歴史的・物的現実(現実)――が互いに緊張しながら、均衡のうちに保たれている。社会における結び目とは、これらの次元が「解けそうで解けない」構造を持ちつつ、ある種の〈固着点〉を作り出す装置である。
エスノメソドロジーとの接続
結び目の理論は、日常的実践における社会秩序の生成を記述する「エスノメソドロジー」とも接続可能である。人びとは、決して「制度通り」「計画通り」には行動しない。むしろ、その都度、場の状況に応じて相互に修正し、意味づけし、新たな秩序を立ち上げる。
この生成過程は、トポロジカルに見れば「ひとつの結び目をどう位置づけ、どう解くか」をめぐる試行錯誤である。問いは常に、「誰がどう誤解し、どこにねじれが生まれ、どう誤読され、どう解かれるか」にある。この意味で、社会は「結ばれ続けている状態」であり、「ほどくことのできない結び目」を扱うことが社会学の仕事になる。
結び目と制度、結び目と逸脱
制度は、結び目を完全に解くことはできない。むしろ、制度とは「結び目の位置を安定させる装置」であり、日々の絡まりを、一定の形式に落とし込む「管理された接続方法」である。
だが、結び目が暴走することもある。それが社会的逸脱であり、時に革命や暴動、時に沈黙や不参加というかたちをとる。トポロジカル・ソサエティにおいて重要なのは、これらの逸脱を「ノイズ」として排除するのではなく、「結び目の強化点」として折り返すことだ。社会的変化とは、結び目の組み換えであり、制度と逸脱の間にあるトポロジカルな運動なのである。
本章では、社会を「ねじれ」「絡まり」「結び」として理解する視点を提示した。これは、動的で生成的な社会理解を支えるトポロジー的思考であり、制度設計のレベルでも応用可能な「局所的トポロジー」としての理論である。次章では、これをさらに倫理の問題へと引き寄せ、分離と近傍という基本的対概念に基づくトポロジー的倫理観を描いていく。
第5章 倫理としてのトポロジー
―― 境界と責任、分離と連帯のための構造
ここまで、トポロジーの概念を用いて社会のかたちを描いてきた。だが、構造を描くだけでは、共同体は持続しない。そこに「どのように関係するべきか」という倫理の視点が必要になる。本章では、トポロジーを「かたちの理論」としてだけでなく、関係と距離の倫理を組織する視座として捉え直す。すなわち、分離と近傍をめぐる倫理である。
境界を引くことの倫理
境界は、排除の装置にもなりうるし、保護の仕組みにもなりうる。現代においてしばしば境界の存在自体が否定される一方で、実際の現場では「誰と関わるのか」「どこまで許容するのか」といった選択が常に迫られている。つまり、境界は不可避である。
トポロジー的思考では、境界は固定されるべきものではなく、「連続的に動かしうるもの」「相互に接触しうる面」として捉えられる。トポロジカル・ソサエティにおいて倫理とは、境界を引くことそれ自体の慎重さであり、「どのように分離し、どのように近づくか」にまつわる持続的な判断である。
ハウスドルフ性と他者の尊重
第2章でも触れた「ハウスドルフ性」は、数学的には「任意の異なる2点が、互いに交わらない開集合で分離できる」ことを意味する。この性質を社会的倫理の次元に翻訳するなら、それは他者を他者として尊重する距離感の確保である。
同一化でも拒絶でもなく、「他者に接近しながらも、他者の分離可能性を保つ」こと――これがトポロジカルな倫理の中核にある。他者の享楽や言語、制度や信念を侵食せず、しかし共に空間を分有するためには、この「分離された近傍関係」が不可欠なのだ。
欠如と共存するということ
ラカンサルヴァティズムの倫理は、「満たされることのない欲望」を前提とし、その不全を否認しない態度に根ざしている。トポロジカル・ソサエティにおける倫理もまた、欠如を埋めないこと、空白を中心に据えることを核とする。
境界や制度が欠如を隠すものでなく、「欠け」を公開する場であるならば、その制度は抑圧ではなく、倫理的な媒介として機能しうる。開集合が閉じられていないのは、「すべてを囲い込まない」ことへの敬意の現れであり、構造的に“空”を含んだ社会こそが、倫理的である。
トポロジカルな共同体とは「近づきすぎない共同体」
あらゆる共同体には、「接近しすぎること」の危険がある。愛国、信仰、友情、恋愛――どれもが、距離を失えば暴力へと変わる可能性を孕む。トポロジカル・ソサエティにおいては、むしろ「近づきすぎないこと」、距離を残したまま繋がることが倫理的実践とされる。
このとき共同体は、他者の違和感や異質性を排除するのではなく、それを保留し、言語化されない「ずれ」を容認することで、自らの形を保持する。倫理は、完全な理解や一致を目指さない「不完全な共存」の中にこそある。
本章では、トポロジーの思考が単なる構造記述を超えて、共同体の倫理的あり方にまで及ぶことを明らかにした。次章から始まる第二部では、こうした倫理的構造を前提にして、それを制度化し、具体的な社会設計へと展開していく。すなわち、トポロジカル・ソサエティの制度的実現に向けた実践編である。
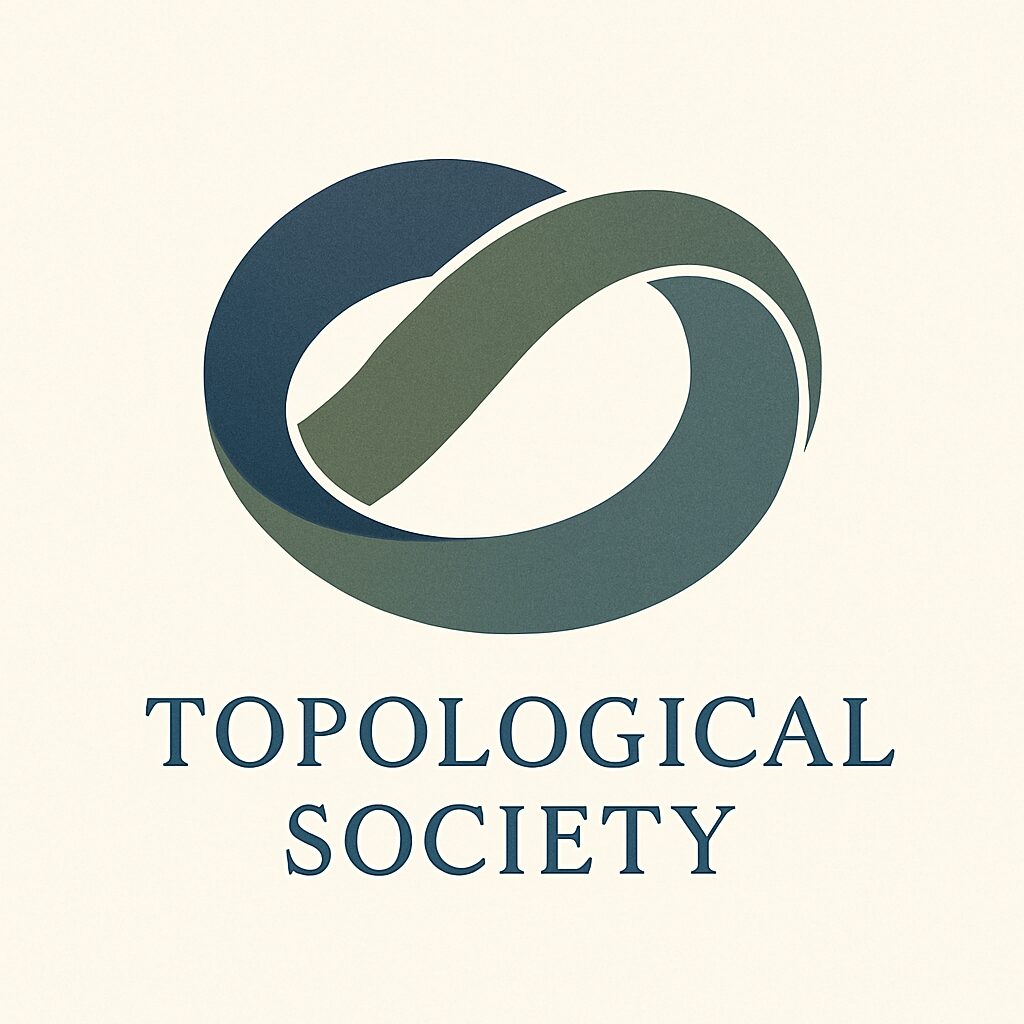


コメント