序章 滑らかな社会は、どこで裂けたのか
⸻
わたしたちは、いつから「つながること」に救いを求めるようになったのだろうか。
孤立せず、対立せず、あらゆる情報が摩擦なく流れる社会。
それはたしかに理想に見える――滑らかで、効率的で、分断のない社会。
しかしその滑らかさの中で、
何かが確実に埋められてしまったのではないか。
⸻
鈴木健が提唱した「滑らかな社会」は、
単細胞から個体、そして社会へと至る進化論的なスケール拡張モデルに基づいている。
情報のやりとりが摩擦なく行われ、制度が敵意や対立を排し、
社会という“ひとつの生命体”が、なめらかに自己組織化していくことを目指す。
しかしそのモデルには、一つの前提が隠れている。
それは、単細胞・人間・社会という三項が、連続的に接続されうるという前提だ。
けれど実際には、
単細胞から人間への変化には進化論的な断絶があり、
人間から社会への拡張には位相的な裂け目がある。
⸻
この本は、そうした“裂け目”を滑らかに埋めようとする思考そのものを問い直す。
滑らかであることが、必ずしも自由をもたらすわけではない。
むしろ、自由とは裂けていることを引き受ける構造ではなかったか。
⸻
エーリッヒ・フロムは『自由からの逃走』の中で、
人間が近代以降に獲得した自由を、同時に不安や孤独と引き換えに抱えるようになったと語った。
人は自由を手にした瞬間、それに耐えられず、
むしろ自ら進んで、権威と同調へと逃げていく。
だがここで問題なのは、
自由が「逃れたいもの」として現れるという事実そのものを、
制度はどう扱えるか、ということである。
逃走される自由こそが、人間の裂け目の本質である。
であれば、制度もまた、裂け目を含んだ構造でなければならない。
⸻
そのために必要なのが、裂け目に耐える思想=不条理の倫理である。
アルベール・カミュが説いたように、世界は不条理であり、
その断絶に対して人ができるのは「反抗すること」だけだ。
だが反抗とは拒絶ではなく、
裂け目の存在そのものを承認し、それでもなお世界と共にあることだ。
⸻
本書が提案するのは、そうした裂け目を、
制度の中心に据えた社会構造=トポロジカルソサエティである。
この構想において自由とは、
選択の幅でもなく、全体性の幻想でもない。
自己のなかに不可避な断絶を保持しながら、なおも選ぶこと。
シェリングが語った中動態的自由。
ラカンが見抜いた象徴の裂け目。
そして、わたしたちが生きるこの制度そのもののトポロジー。
⸻
われわれは、あまりにも滑らかに自由を定義しすぎた。
自由とは、裂けていることに耐える構造なのだ。
第一章 欠如から始まる自由
自由とは、本当に望まれているものなのだろうか。
それは常に、賛美され、憧れられ、時に命をかけて求められる。
しかし歴史が示すのは、人間は自由を得た瞬間、それに耐えられなくなり、逃走してきたという事実である。
エーリッヒ・フロムはその著書『自由からの逃走』において、
近代における自由の二重性を見抜いた。
個人が宗教的・経済的権威から解放され、形式的な自律を獲得したとき、
同時に孤独、不安、選択の重圧にさらされるようになった。
そして人は、こうした内的な裂け目から逃れるために、
新たな権威――ファシズムや全体主義、同調圧力へと自らを再拘束する。
この構造は、単なる歴史的逸脱ではない。
自由そのものが“裂け目を孕んだ存在”であることを意味している。
現代社会が提案する「自由」は、往々にして
選択肢の多さ、自己決定権、滑らかな移動性として語られる。
だがその自由は、どこにも傷をつけずに滑っていく自由であり、
葛藤も裂け目も、制度も他者も、すべて透明化された世界の中で成り立っている。
しかし本当に人間が生きる自由とは、
そのような滑らかな空間には現れない。
自由とは、選択肢の豊かさではなく、
選ぶことにおいて何かを失うこと、欠けること、切り捨てることである。
選ぶという行為の本質は、
すべてを持てないという欠如に耐えることにある。
このとき、自由とは「滑らかさ」ではなく「裂け目」の中にある。
この裂け目を、心理的にどう耐えるかという観点から、
わたしたちの思想は「ユニティ・コンプレクス」という概念を導入する。
ユニティ・コンプレクスとは何か
⸻
ユニティ・コンプレクスとは何か。
「一つでありたい」「裂け目を持ちたくない」「分断を認めたくない」という心理的傾向である。
それは個人のレベルでは、「矛盾を抱えることが怖い」「不一致を避けたい」という回避傾向として表れ、
集団レベルでは、「国家」「民族」「宗教」などの名のもとに、単一性への幻想として現れる。
⸻
この傾向は、歴史的には以下のような事象に通底している:
⸻
【1. 全体主義の欲望(ナチズム・ファシズム)】
• エーリッヒ・フロムが『自由からの逃走』で分析したように、
ナチズムの台頭は、自由を得た個人がその不安定さに耐えられず、強力な統一の象徴=国家と民族に“逃げ込んだ”結果である。
• 「ドイツ民族の純血性」「ユダヤ人という“裂け目”の排除」など、
“一つでありたい”という欲望が、現実の複雑性を抑圧する形で制度化された。
⸻
【2. 近代国家における“国語”と“単一民族”幻想】
• 多くの近代国家は、「ひとつの言語・ひとつの文化・ひとつの国民」を前提として制度を整備してきた。
• 実際には民族も言語も多様だったにもかかわらず、
教育・法律・メディアを通じて“統一された主体”が創出された。
• その背景にあるのもまた、制度に裂け目(多様性・翻訳・異物)を持たせたくないというコンプレクスである。
⸻
【3. 現代における“過剰な共感”と“ポリティカル・ユニフィケーション”】
• SNSなどの空間では、異なる意見よりも「共感の一致」が重視され、
わずかな異論が炎上や排除の対象となる。
• また、ポリコレの名のもとに、すべての違いが「同一の規範に吸収される」傾向もある。
→ 統合は進むが、裂け目を容認する余地はどんどん失われる。
⸻
【4. ユニティ・コンプレクスの構造的特徴】
• “中心と境界を固定しようとする”力学をもつ。
• 境界のゆらぎ(アイデンティティの不安定性)を嫌い、
• 境界の外部(制度外・異文化・反論)を脅威とみなす。
• そのため、制度は「透明な共通基盤」の幻想を維持するよう設計されてしまう。
⸻
しかし、現実の人間も社会も、常に複数性・矛盾・非同一性を抱えている。
制度もまた、「すべてを包含できない構造」「翻訳不可能な裂け目」を構造的に含む必要がある。
⸻
ユニティ・コンプレクスにとらわれた制度は、
欠如を排除しようとして、かえって自由を消してしまう。
だが本書はむしろ主張する。
自由とは、欠如を引き受けた構造である。
分断や異物を処理不能なバグではなく、制度内部に“残響”として位置づける。
それが、裂け目の自由なのだ。
⸻
自由を守るには、“一つにならない勇気”が必要である。
欠如を制度の内部に保存せずして、
自由は決して長続きしない。
第二章 不条理の倫理——カミュにおける裂け目
⸻
世界は理不尽である。
それが、アルベール・カミュの思想の出発点だった。
世界は意味を与えてくれず、神は答えを返さず、
人間は、生きていること自体の理由を説明できないまま、
それでも朝を迎える。
⸻
この断絶。
この、理解しようとしてもつながらない「世界と人間のあいだ」の断絶。
それが、不条理(l’absurde)である。
⸻
カミュにとって、不条理とは問題でも敵でもない。
それは前提であり、
この前提を拒絶することなく、しかし屈することもなく、
“反抗(révolte)”という倫理的態度によって耐えることこそが、人間の尊厳である。
⸻
不条理に対する三つの態度(カミュ)
1. 自殺
不条理から逃れるために、生の意味ごと拒絶する。
→ カミュはこれを否定する。「自殺は答えではない」。
2. 宗教的飛躍(信仰)
説明不可能な世界を、神の存在によって強引につなげてしまう。
→ カミュはこれも否定する。「それは誠実ではない」。
3. 反抗(révolte)
不条理を認識し続けながらも生きることを選ぶ。
→ 「人は世界に意味を与えられない。それでも意味を問うことをやめない」。
⸻
ここに、裂け目を倫理化する態度がある。
⸻
反抗とは、何かに従わないということではない。
むしろ、つながらないことに耐える勇気であり、
つなげようとしないことへの誠実さである。
カミュの反抗者は、滑らかに閉じようとする社会の構造に対して「裂けたまま立つ」者である。
⸻
この姿勢は、そのまま制度のあり方にも転写されうる。
⸻
制度はなぜ“不条理”を否認しようとするのか?
• 制度は秩序を好む。意味のある関係を重視する。
• 不条理(裂け目)は、予測不可能性・不透明性・非合理性を孕むため、制度はそれを例外として排除したくなる。
• しかし、実際には不条理は制度外にあるのではなく、制度そのものの構造に内在している。
⸻
制度が“あらゆる例外に対応できること”を目指すとき、
制度は自由を見失う。
制度はむしろ、「対応できない裂け目」を含みながらも、運用しつづけられる柔らかさを持つべきなのだ。
⸻
ここで、カミュの反抗倫理と本書の社会構想が重なる。
• カミュの反抗者は、世界の不条理に耐えることで人間性を守った。
• トポロジカルソサエティの市民は、制度の裂け目に共振することで自由を守る。
⸻
裂け目を否認する制度は、いつかその裂け目によって崩れる。
裂け目を共に引き受ける制度は、決して完成しないが、崩れない。
⸻
制度が「反抗すること」を内包する――
つまり、制度の中に“不条理に応える自由な空間”を残すこと。
この不完全な制度、決して閉じることのない社会、
それこそが、“裂け目の自由”を生きる共同体の原型である。
第三章 トポロジカル自由論の基礎
自由は、構造である。
そしてその構造は、単に開かれているのでも、閉じているのでもない。
それは、欠如を中心にして編まれた、裂けた構造である。
これまで、自由はさまざまに定義されてきた。
・「選択肢があること」
・「外部からの干渉がないこと」
・「自己決定できること」
だがこれらの定義は、自由を“滑らかな空間”の中に閉じ込めてしまう。
自由を保証するには、まずその空間そのものの構造を見直さなければならない。
トポロジーの言葉で自由を語るとき、何が変わるのか?
トポロジーとは、
物体の「形そのもの」ではなく、「穴や繋がりの有無」に注目する数学的視点である。
たとえば:
- 球とサンドイッチはトポロジー的には同じ(どちらも“穴がない”=単連結)
- ドーナツとマグカップも同じ(“穴が1つ”ある)
つまり、自由もまた、その“位相的な形”で捉え直すことができるのではないか。
自由のトポロジー:単連結的自由 vs 非単連結的自由
- 滑らかな自由=単連結的構造
→ 閉じた空間の中で、常に意味が連続していて、裂け目がない。
→ ユニティ・コンプレクスが支える幻想 - 裂けた自由(トポロジカル自由)=非単連結的構造
→ 欠如がある。構造に穴がある。
→ だが、その穴を受け入れることでこそ、「制度の外」に出る自由が保証される。
ホモトピー的自由とはなにか?
- トポロジーでは、「形を連続変形して同じものと見なす」関係をホモトピーという。
- この考えを社会に応用すると、「制度の形が変わっても、ある自由が保たれている」状態と見なせる。
- 逆に言えば、自由とは「構造の不変性」ではなく、「構造の変形可能性」にこそ宿る」。
だから自由とは、「安定していること」ではなく、
「揺れに耐えうる構造を持っていること」である。
トポロジカルソサエティにおける自由の定義(暫定)
自由とは、
制度の裂け目を保持したまま、
自らの構造を変形する余白を持ちつづけること。
この定義は、個人の選択だけでなく、
制度や共同体の「変形耐性」にも適用される。
- 社会がある時点で自由であるかどうかは、
「誰かが制度の外に出られる構造が残されているか」にかかっている。 - 制度が欠如を否認し、完全な閉じた構造になれば、
たとえ選択肢が多くても、それは自由ではなく統御である。
トポロジカルな自由とは、
裂け目に耐え、変形を許容する社会のリズムそのものなのだ。
滑らかに繋がる自由ではなく、
つながらないことに耐える自由こそが、
真の制度変形力を持っている。
第四章 ラカンサルヴァティズムの社会実装
「社会はなぜ、裂け目を拒むのか?」
その問いに対して、ラカン的答えはこうである。
社会が裂け目を否認するのは、言語=象徴が本質的に“欠如”を中心に据えているからだ。
そしてその欠如こそが、主体を生み、欲望を駆動し、自由を可能にする。
ラカンの理論において、
人間は最初から言語=象徴界に巻き込まれて生きる存在である。
だがその言語には、決して埋めることのできない抜け=裂け目(manque)がある。
これは単なる“言い損ね”や“認識の誤差”ではない。
むしろ、すべての意味はこの“欠け”を中心にして回っている。
「欠如を排除する制度」vs「欠如を保持する制度」
現代の多くの制度は、ラカンのいう「象徴の欠如」を不具合として扱う。
- 「すべてが説明可能であるべきだ」
- 「制度は例外なく運用されるべきだ」
- 「意味は常に明確に伝達されるべきだ」
しかしラカンは逆に言う。
意味は常にズレ、語り得ないもの=“対象a”が残されるからこそ、人間は自由を感じるのだ。
つまり、自由とは“象徴の穴”に耐えうる構造を持っていることであり、
制度もまた、意味が閉じきらない空白を持ち続けることで、
主体と社会の接点に裂け目を確保する必要がある。
ラカンサルヴァティズムとはなにか?
この本でいう「ラカンサルヴァティズム」は、
ラカンの欠如理論をベースに、制度設計の倫理的原則を導く思想的実践である。
それは単なる精神分析の応用ではない。
むしろ、「人間は欠如によって制度と接続される」という前提を、
制度そのものの形にまで反映させようとする構想である。
制度=象徴構造としてのトポロジー
ここで再び、トポロジーがラカンと結びつく。
ラカンはボロメオの輪というトポロジカル図形を用い、
現実・象徴・想像の三界が「互いにズレながらも繋がっている状態」を示した。
このモデルを社会に応用すれば、
制度とは「すべてを統合する輪」ではなく、
「ズレを許しながら崩れない三重構造」として設計されるべきだとわかる。
ラカンサルヴァティズムとは、裂け目の倫理に基づいた社会保守思想である。
保守とは、完全性の維持ではない。
むしろ“不完全性を壊さずに保つこと”である。
滑らかな社会は、すべてを言語化し、つなげ、最適化しようとする。
だがラカンサルヴァティズムが提案するのは、
制度の中に“意味にならない場所”を残す勇気である。
それがなければ、制度はやがて人間を抑圧し始める。
それがあれば、制度は“耐えうる裂け目”として人間の自由を受け止め続ける。
終章 裂け目の自由へ――制度のための詩
⸻
制度は、なぜ詩を必要とするのか。
この問いは、おそらく逆立ちしている。
なぜなら、詩は制度を必要としないからだ。
詩は制度の外に生まれ、意味の外側を歩き、言語の裂け目に棲む。
だがそれでも、わたしたちが自由な制度を構想するためには、
詩的な構造を制度のなかに受け入れなければならない。
⸻
ここでいう「詩」とは、美辞麗句でも感傷でもない。
むしろ、「語りえないものが制度に残した“構文のゆらぎ”」である。
• 意味にならなかった一節
• 理解されなかった発言
• 定義されなかった沈黙
それらを“消す”のではなく、“制度の中に残す”。
それが、トポロジカルソサエティの核心である。
⸻
詩的制度とはなにか?
詩とは、意味の全体性を拒否する構文の試みである。
そして制度が詩的になるとは、意味の全体性を保持しない構造を設計することを意味する。
⸻
この構想の具体例はまだない。
それは未来において実装されるものだろう。
だが、わたしたちはそのための原理をすでに手にしている:
• 欠如から始まる自由
• 不条理に耐える倫理
• 構造的ズレを保つ制度
• トポロジカルに変形しうる共同体
それらすべてが、“語りえないが制度に宿る詩”として、未来の社会に刻まれていく。
⸻
詩は制度に何をもたらすか?
• 完全性を拒否する余白
• 同調しきらないリズム
• そしてなにより、「わからないことを残す勇気」
⸻
わたしたちは、欠如を排除しない制度を望む。
それは、完全に滑らかではなく、ところどころに詩のような“裂け”を持つ。
その裂けこそが、自由の居場所である。
⸻
自由とは、制度のなかに詩が“残ってしまうこと”である。
完全に意味化されることを拒む構文。
説明されなかった声。
それが制度の中で響きつづけるとき――
その制度は、まだ自由である。
⸻
あとがき 滑らかさの向こうに裂け目を据えるために
この本は、ある意味でひとつの不安から始まっている。
私たちは日々、滑らかにつながる社会のなかで生きている。
衝突は避けられ、意思決定は最適化され、葛藤はアルゴリズムの背後へと吸収されていく。
そこには安心と効率がある。
だが同時に、語られなかった声や、居場所を見失った構文が、静かに消されていく感覚もある。
「滑らかな社会」という構想は、
本来は分断を乗り越え、より良い共生の形を模索する知的努力だった。
だがそこには、人間と社会のあいだにある「裂け目」が、
あまりにスムーズに、あるいは前提として無効化されていた。
この裂け目――
それは、選びきれない自由、語りえない欲望、制度に回収されない意味の残響。
つまり、自由そのものの出発点だった。
わたしたちは、滑らかな自由ではなく、
裂けたままで成立する自由を守らなければならない。
そのために本書では、
- フロムの「逃走される自由」
- カミュの「不条理に耐える倫理」
- シェリングの「中動態的な意志」
- ラカンの「象徴界の裂け目」
を通じて、自由を「裂け目に耐える構造」として再定義してきた。
そして最後に提案したのが、トポロジカルソサエティである。
これは、すべてを意味で埋めない制度。
翻訳不能な部分を制度の中に残す共同体。
誰かの語れなかった詩が、沈黙のまま保存される空間。
それは、「わかりあう」ことのための社会ではない。
「わかりあえないまま、共にいる」ことを可能にする構造である。
滑らかな社会は、「全部つながること」によって安心を与えようとする。
トポロジカルソサエティは、「つながらなかった場所を制度に残すこと」で、自由を保とうとする。
そのちがいこそが、
わたしたちの未来にとって決定的な分岐点なのだと、
本書は静かに主張する。
裂け目を見つめること。
それを制度から消さず、詩として、構文として、痕跡として、残すこと。
それが、わたしたちの自由の最後の砦になるかもしれない。
制度の中に、わずかな詩の余白を。
その詩がある限り、制度はまだ自由である。
参考文献
⸻
I. 滑らかな社会とその批判的検討
• 鈴木健『滑らかな社会とその敵』勁草書房, 2013年
• 濱野智史『前田敦子はキリストを超えた』朝日新聞出版, 2012年(情報社会の構造的滑らかさについて)
• 藤村龍至『プロトタイピング—模型とつぶやき』INAX出版, 2008年(「滑らかさ」の建築的比喩)
⸻
II. 自由・欲望・主体の理論的基盤
• エーリッヒ・フロム『自由からの逃走』日高六郎 訳, 東京創元社, 1965年
• アルベール・カミュ『シーシュポスの神話』窪田啓作 訳, 新潮社, 1970年
• フリードリヒ・シェリング『人間的自由の本質』長谷川宏 訳, 以文社, 1997年
• バタイユ『呪われた部分』中山元 訳, ちくま学芸文庫, 1998年(自由と過剰・裂け目の接点)
⸻
III. 精神分析とラカン理論の応用
• ジャック・ラカン『エクリ』Jacques Lacan, Écrits.
• 小出浩之『ラカン 欲望の哲学』講談社現代新書, 2007年
• 斎藤環『ラカンはこう読め!』青土社, 2000年
• 松本卓也『「心は遺伝しない」』講談社現代新書, 2021年(現代社会とラカン的裂け目)
⸻
IV. トポロジー、構造思考、制度設計に関する理論
• 杉浦光男『トポロジー入門』岩波書店, 2006年
• 増田直紀『トポロジカル物質とは何か』講談社ブルーバックス, 2018年(比喩でない実践トポロジーの例)
• デヴィッド・ボーム『全体性と内蔵秩序』講談社, 1990年(非滑らかな思考の構造性)
• 宮台真司『14歳からの社会学』世界思想社, 2000年(制度的断絶と社会構造)
⸻
V. 詩と構文、制度の境界で
• 伊藤比呂美『とげ抜き 新巣鴨地蔵縁起』講談社, 2010年(詩と制度のあわい)
• 斉藤倫『世界は記号でできている』筑摩書房, 2020年(意味を拒む詩と構造の哲学)
• マルグリット・デュラス『愛人 ラマン』河出書房新社, 2000年(詩と裂け目の語り)
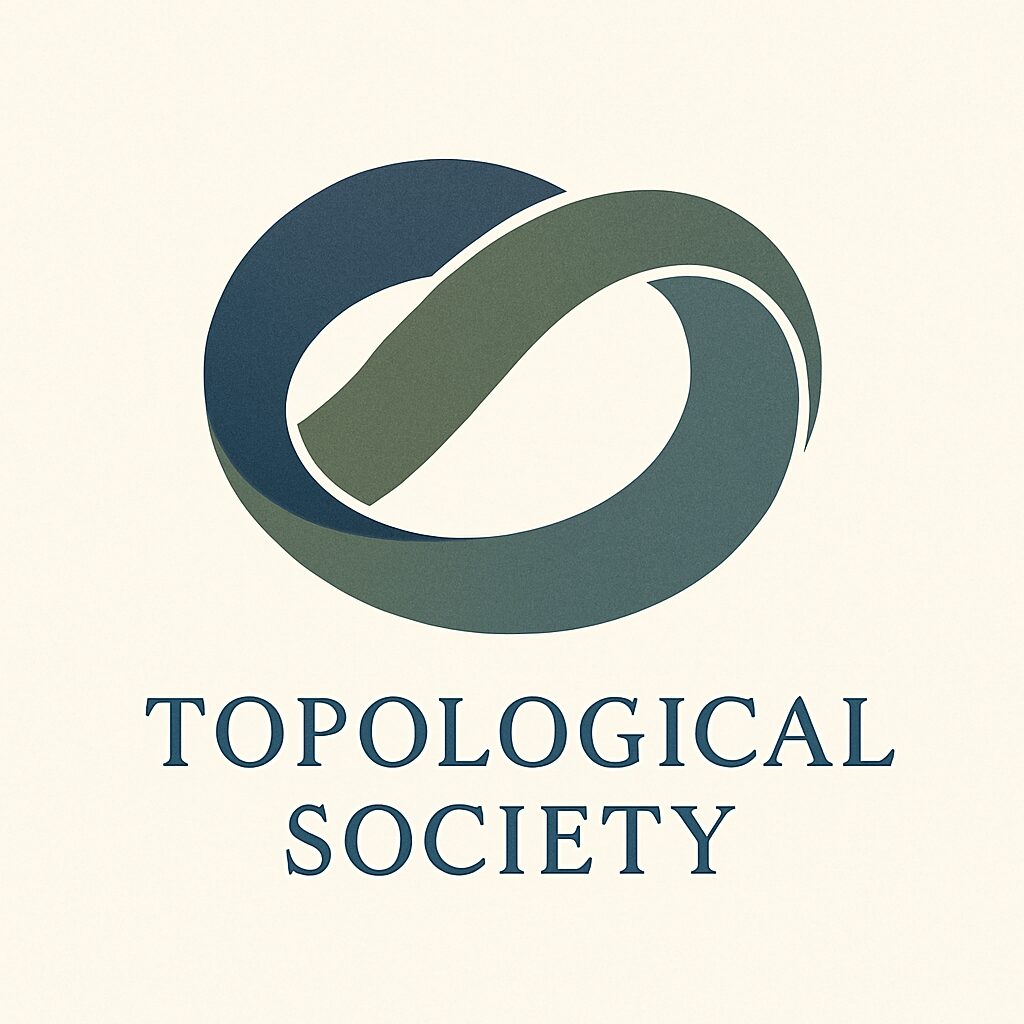


コメント